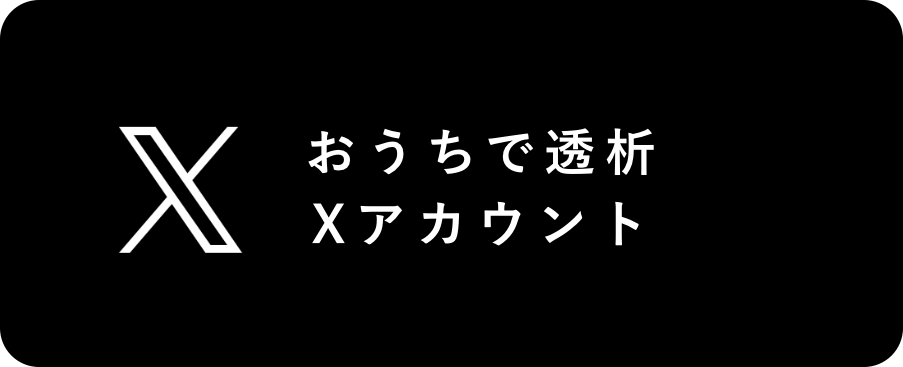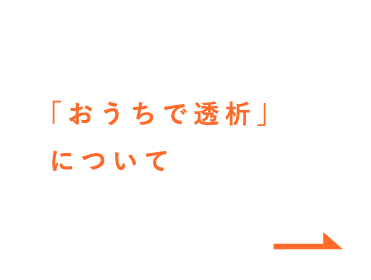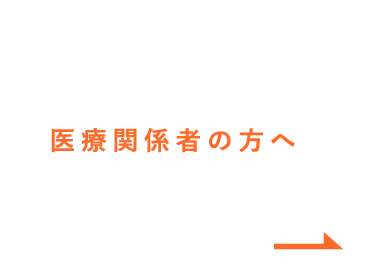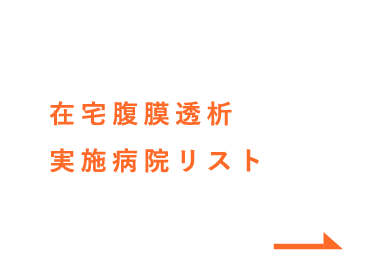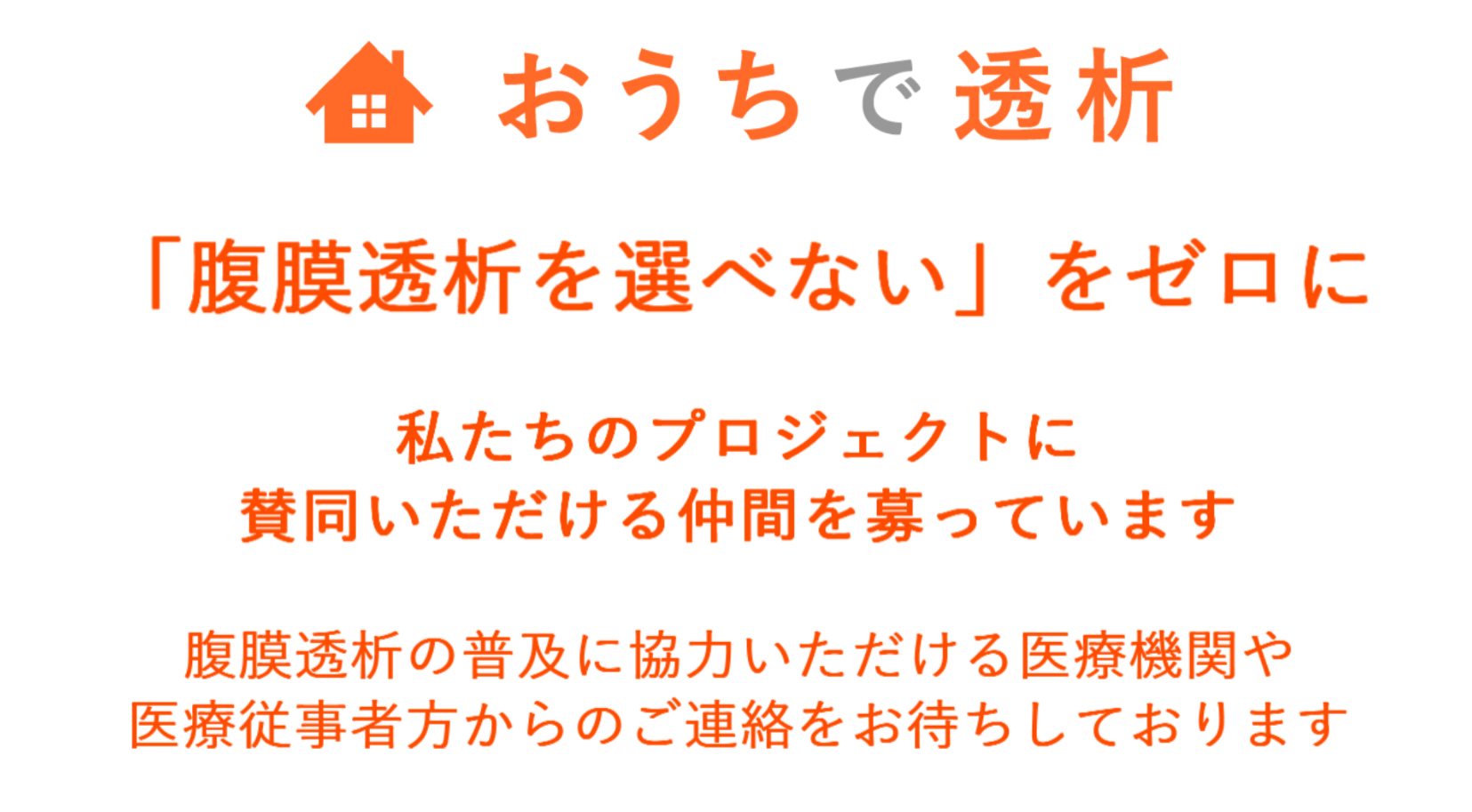松本先生インタビュー⑤腹膜透析の進歩


松本先生インタビュー⑤腹膜透析の進歩
文字サイズ
松本先生インタビュー⑤腹膜透析の進歩
[松本先生インタビュー⑤腹膜透析の進歩]
- 川原腎・泌尿器科クリニック(鹿児島県姶良市)
腎不全外科科長・腹膜透析センター長
松本 秀一朗 様
聞き手:
- 医療コンサルタント 大西 大輔(MICTコンサルティング株式会社 代表取締役)
- 医療法人明洋会 理事長 柴垣 圭吾 様
松本先生: 今、統計上腹膜炎は、大体1人の患者が5年に1回なるかどうかで、腹膜炎の心配はほとんどいりません。
そして除水の問題、いわゆる体液コントロールの問題もイコデキストリン透析液を使うことで、簡単にできるようになりました。
さらに、腹膜硬化症という大変な問題があったのが、2004年に中性液、そしてブドウ糖の分解産物GDPを少なくした新しい透析が開発されたことで、腹膜硬化症はほとんど起きなくなりました。
そのため、2004年以降、腹膜硬化症EPSの癒着剥離の手術を全くしなくなりました。一番新しい2017年のオランダEPSレジストリーでは、0.14%なので、ほとんどないと言って良いのではないでしょうか。
ですから、腹膜透析は5年から8年はもちろん、10年以上は絶対に問題なく、僕自身の経験では34年腹膜透析を行ってきて、移植した患者さんもいますし、徳島の病院では44年ぐらいやっている方がいると聞いたことがあります。
さらに中性液の時代になり、EPS腹膜硬化症の問題の心配がいらなくなったので、導入時に患者さんに、「5年とか8年で離脱だよ」という話はしなくて良くなりました。
さらに、オートサイクラー(自動腹膜還流装置)で、自動的にお腹に液を入れたり出したりすることができるので、寝ている間にできて、患者さんの生活リズムをそのまま維持できます。
そして最近のものはインターネットに接続され、患者さんの情報や治療モードの変更なども簡単にできるようになりました。最近JMSさんも遠隔モニタリングを出し、医療機関にて、家にいるたくさんの患者さんを安定して管理できるようになりました。
僕らのところでは、今腹膜透析の患者さんが90数名いますが、6~7割の人がこのAPDを使っています。医者は僕一人ですが、こういうシステムがあるおかげで安定して管理できます。
バイタルサインを入力してもらえますし、JMSの後自動的にBluetoothで情報が飛び自動入力されます。そういうのも簡単に見られるようになりました。
腹膜透析は20年ぐらい前とはもう全く違います。
実は、僕らが今考えているような「高齢者向けの腹膜透析は良い」というコンセプトは、20年ぐらい前に、すでに高齢者腹膜透析研究会ゼニーレPD研究会で非常に詳細に語られて議論されていました。
「高齢者の腹膜透析」というこの本、もう絶版になってしまっていますが、この内容は今読み返しても本当に素晴らしい内容で、時代を先取りしていたと思います。
済生会八幡病院の中本先生は、残念ながら2年前にお亡くなりなってしまいましたが、北九州PDラストという終末期の透析患者さんに腹膜透析をやろうとされていらっしゃいました。
基幹病院で血液透析で弱っている方を腹膜透析にして、そして在宅で透析クリニックでフォローしたらどうかと考えていらっしゃいました。
その時に、ちょうどNTTドコモのiモードがあり、そういうものを使ってインターネットで情報交換したらどうかと提案されていました。
当時、中本先生たちや女子医大におられた中元先生たち、秋葉先生たちと活動されていました。まさに20年前、時代を先取りしていたなと思います。
このコンセプトはそのまま20年止まっていたわけですが、さっき言った2000年ぐらいからiモードが出たり、カメラ付き携帯が出たり、電子カルテが出たり、2007年ぐらいにはiPhoneや、今収録しているYouTubeが出たり、2008年ぐらいにAndroidの携帯が出たり、FacebookやTwitter(現X)などSNSが普及し始めて、そして今インターネットの普及率もこの20年ぐらいの間に一気に90%ぐらいまで普及しました。
これにより、いわゆる腹膜透析を始め、在宅医療と病院医療の垣根がなくなって、高齢者腹膜透析研究会で語られていたようなことが、リアルになったのです。
自分でできない患者さんに対して、手伝いながら腹膜透析を実施することを「アシステッドPD」と言いますが、2016年当時の「臨床透析」の特集では「まだまだコンセプト先行です」と言っていましたが、今年ぐらいの特集になると、「もういよいよ新しい時代が到来している」というような言葉になっています。
実際、僕らの外来では、もうクラウド型の電子カルテによって、どこでも患者さんの情報を見られますし、処方もできます。それからリモートによる複膜透析の管理ソフトで患者さんの治療状態をどこでも見ることができます。
そしてSNSなどを始めとした連携ツールを使うことで、どこにいても病院と同じような医療を、場合によっては病院以上のクオリティの医療を提供できる時代になりました。
今僕らはたくさんの患者さんを診ているのですが、全然負担なく診られるのです。