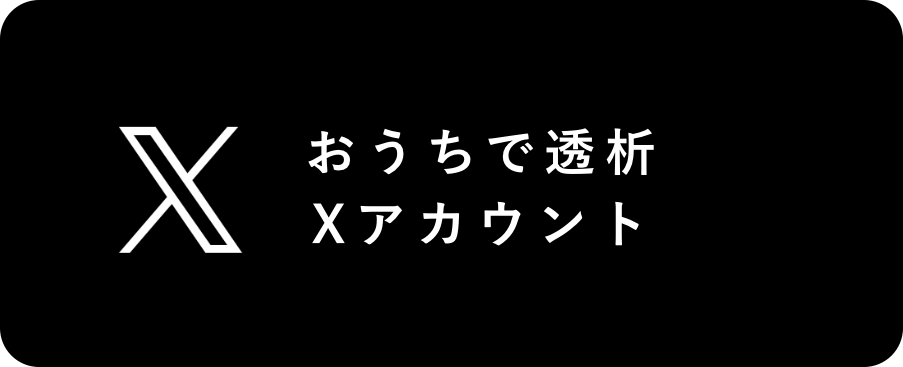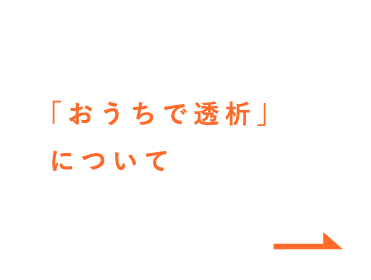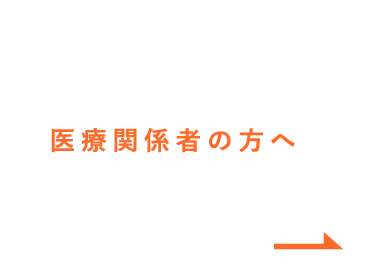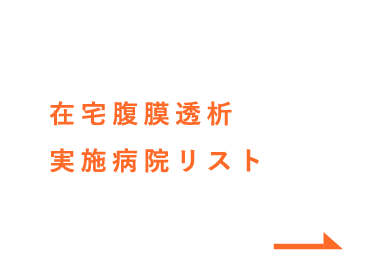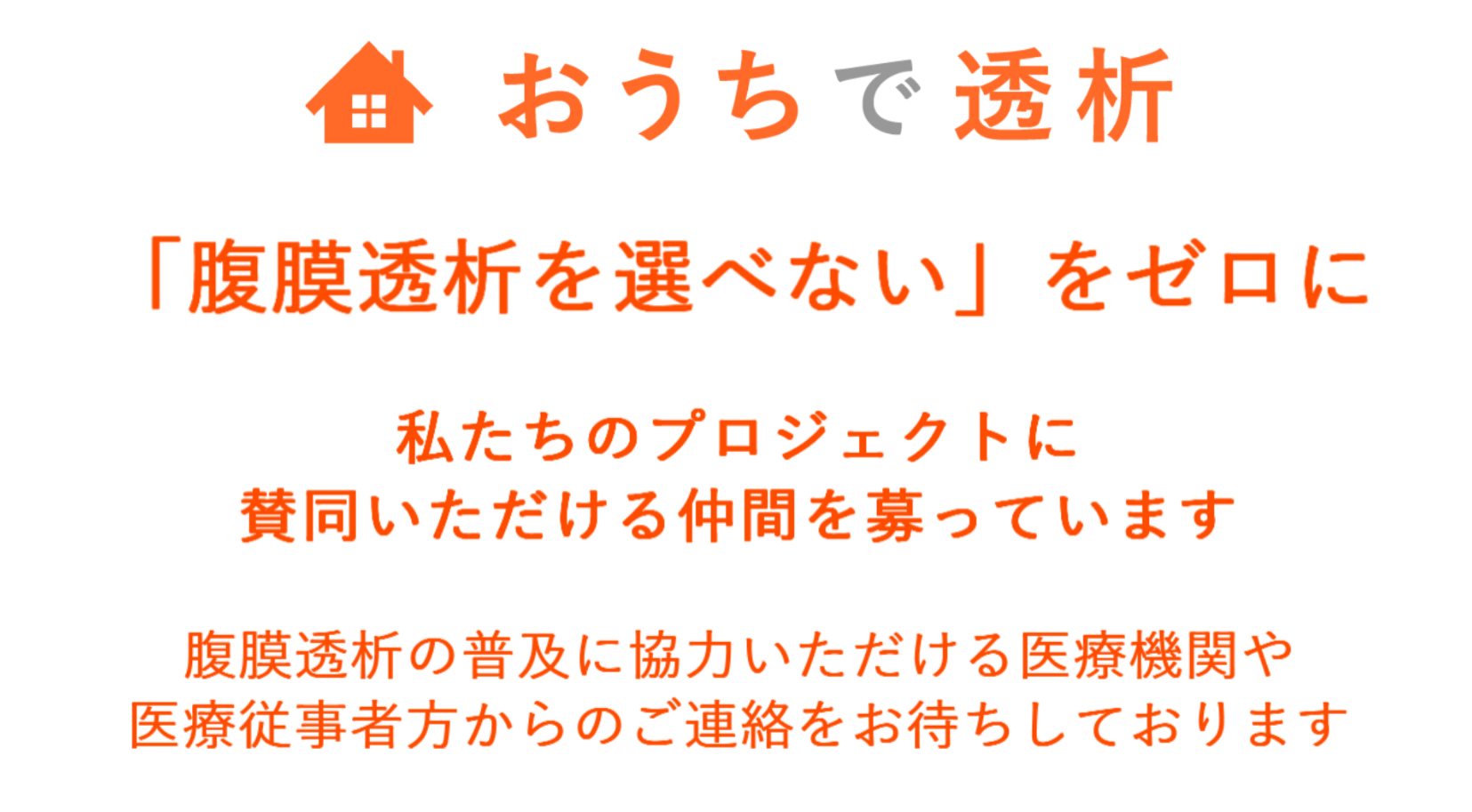腹膜透析鹿児島モデルインタビュー①


腹膜透析鹿児島モデルインタビュー①
文字サイズ
腹膜透析鹿児島モデルインタビュー①
[腹膜透析鹿児島モデルインタビュー➀]
- 川原腎・泌尿器科クリニック(鹿児島県姶良市)
腎不全外科科長・腹膜透析センター長 松本 秀一朗 様
看護師 益満 美香 様
聞き手:
- 医療コンサルタント 大西 大輔(MICTコンサルティング株式会社 代表取締役)
- 医療法人明洋会 理事長 柴垣 圭吾 様
大西: 今日は鹿児島に来ております。まずは自己紹介をお願いします。
松本先生: 鹿児島に住んでいる松本です。よろしくお願いします。
柴垣先生: 柴垣医院の柴垣です。よろしくお願いいたします。
益満さん: まつもとクリニックでPD(腹膜透析)のナースをしている益満です。
大西: 今日、鹿児島に来てPD(腹膜透析)モデルというものを見せていただきました。鹿児島だから、松本先生だからできるのではないか、という話はあるかと思いますが、今日はそのあたりを本当にそうなのかと思いながら、質問をベースに考えていきたいと思います。
柴垣先生、東京で鹿児島のようなモデルを構築できなそうだなと思ったことはありますか?逆に参考になると思ったことはありますか?
柴垣先生: 施設でPD患者さんを引き受けてくれるところがあるかどうか、というところに困難があるかなという印象があります。
大西: 東京では施設がPD患者さんを受け入れないのではないか、と思われたのですね。
松本先生: そんなことはないのではないでしょうか。施設はどこも日本中同じですので、医療としての腹膜透析をできるかどうかという点がポイントになります。
今日往診に同行してもらいました。柴垣先生も聞いていただいたと思いますが、施設の看護師さんで誰一人「腹膜透析が大変です」という人はいなかったですよね。
むしろそこで腹膜透析の患者さんを支える看護ができることに喜びを感じていたり、本来の医療業務としての看護師の仕事を施設でもできるということに充実感を感じている方が多いのを感じていただけたかと思います。
ですから、医療としての腹膜透析が可能かどうか、という点に関しては、東京も鹿児島も全く同じかと思います。
大西: 施設がPDを可能にするためにはどうすれば良いのでしょうか?
益満さん: そうですね。私たち医療者がサポートするということが重要かと思います。
私達は、施設の看護師、訪問看護師、全員が同僚として色々なことを一緒に考えて一緒に対応していく、ということをモットーにしているので、そういう姿勢も重要かなと思います。
大西: ここはキーワードかと思います。
仕掛ける側がまつもとクリニック、受ける側が施設という構図の中で、いかに施設の人に「大丈夫」と思ってもらえる環境を整備するかが大事ではないかと思います。
また、「知らない」ということも結構大きな障害ではないでしょうか。「施設では受け入れられない」と思い込んでしまっている医療者は多いのではないでしょうか。
柴垣先生: 知らない食べ物は食べられないですからね。
大西: それがまず一つ突破口になりそうに思います。
私達が東京でこのモデルを構築しようとする時、協力してくれそうな施設に片っ端から連絡し、一緒にやりませんか、と口説くことが大切なのかと思いました。
今日、施設の方々に「PDは大変ですか?」と質問してみましたが、どなたも「大変ではない」と答えていましたが、最初は大変だと思っていたのでしょうか?
益満さん: 最初は、やったことがないので大変かな、と思った方もいらっしゃったと思います。
松本先生: 「透析を施設でやる」と言うと、「血液透析を施設でやるのか」と勘違いしてしまうようです。知らない人は皆そう思うわけです。
ですが、こういうものですよ、と見せてあげて、勉強会も必ずやると安心して受け入れてもらえるわけです。
それから、僕らが必ず言う言葉があります。「患者さんが家で普通に自分たちでできている医療なので、当然できますよね」という言葉です。実際にやってみたら全く何ともないと思ってもらうという事ですね。僕らのその言葉に嘘はありませんので。
1回やって問題なければ、あとはもう、皆同じです。他の施設さんでも同じように受けてもらえます。
そしてその老人施設の経営者などの意思決定をする人たちが「理念を共有してやろうよ」と言ってくれれば、スタッフも当然やるということになるわけですね。
老人施設は今までみたいに医療依存度の低い方だけを受け入れる施設では成り立たなくなってきています。実際、ある程度医療依存度の高い方も積極的に受け入れていこうという施設が増えています。
これは鹿児島に限らず、東京でも全く同じかと思います。地域の中でパートナーシップを組めるところを見つけて、そこと共に共存共栄関係を築くというビジネスマインドも同時に必要です。結果的にそれは患者さんの幸せや幸福につながります。
柴垣先生: 東京も鹿児島も高齢化率というのは今後も上がっていくわけです。鹿児島は人口も減るので、終末期の高齢者の実数はあまり増えないかもしれませんが、高齢化率が上がるのは東京も鹿児島も一緒です。
ただ実数がどんと上がってしまうのが都心部です。東京都は1300万人の人口がいます。鹿児島県の10倍ですね。そこに対する備えというか、そういうインフラ整備はまだ東京はできてないだろうなと感じます。どうするつもりなのか…。
大西: そこに関しては、鹿児島に特別何かが元々あったわけではなく、松本先生たちが仕掛けていき、整備することで、成功モデルを構築することができたので、ある意味東京でも同じことをやっていく、ということが考えられるかもしれません。
行政に期待するのではなく、誰かが旗を振り、それについていく人を増やしていくという地道な活動になるかと思います。
益満さん: 私たちが活動を始めたのは12年前でした。その頃は訪問看護を使っている施設はなく、そこからの開拓でした。
PDはどこでもできるので、例えば慢性期病院でもできますし、HD(血液透析)施設がないところでもできます。そのようなことを説明しながら仲間を増やしてきました。
社会的に入院を強いられている方もPD医療を提供することで、そこから在宅という道ができるので、それを立証して来たと思います。
大西: PDであれば施設側もあるいは医療機関側の設備投資も不要ですから、立ち上げやすいのではないかと思いますね。
柴垣先生: この国はもうお金がないので、そうせざるを得ない、ということですね。
大西: 難しそうだなと思ったのは、看護師さんや訪問看護師さん、施設のスタッフに説明に回る部分です。柴垣先生、ご自身が全部回る、ということに関してどう思いますか?
柴垣先生: 施設の人には医師である私が回るのは良いと思いますが、看護師さんには看護師さんが行った方が良いように思います。
大西: それに関して、今日気づいたことは、鹿児島モデルでは医師(松本先生)とスーパーナース(益満さん)がセットである、ということです。益満さんが看護師への説明という役割を担っていらっしゃいます。
そこで、益満さんのマインドを話して欲しいと思います。益満さん、松本先生に、例えば、オペ室を立ち上げるとき、PDを始めるとき、何と言われたのでしょうか?
益満さん: 「できない理由ではなく、できる方法を考えて。まずはやってみて。」ということです。
大西: この、「できない理由を考えるのではなくて、できる理由を考える」というマインドは、松本先生イズムですね。当然、できない理由を考えたらできないですから。できる理由を考えたらできます。
言葉のあやではなく、本当にそうなる、というのが実証実験で分かったのかなと思います。柴垣先生はどうでしょう、先生もこれまでできる理由を考える方針でやってこられたのでしょうか?
柴垣先生: 誰もやったことがないという道ですから、やはりいろいろ考えて試行錯誤しながらやっていくということだと思います。
大西: そこで一つ僕は感じたのは、誰もやったことがないという風に考えてやったからできたのではないかなということです。松本先生は誰の真似もせず、ご自身で考えて作り上げてきました。
もし私達が東京で似たようなことをやろうとした場合、鹿児島で12年かかった道筋を私達はもっと短くできるかもしれませんね。やったことのあることを、今日教えてもらったということですので。
柴垣先生、改めて今日の感想をお願いします。
柴垣先生: 施設もそうですが、訪問看護師さんともまずはできるところと組んで、徐々に広げていく、ということですかね。
大西: 一つのポイントは、ネットワークを作る時の難しさがあるかもしれないと感じましたが、松本先生、ネットワークを作る、という意識はありましたか?
松本先生: ネットワークを作るのは難しくもなんともありません。特に柴垣医院さんは地元で知名度があるので簡単かと思います。
私などは、始めた時に知名度ゼロからのスタートでした。むしろ徳洲会グループにいたことで、地域の中では疎外されていました。紹介も何もない、そういう中でもできています。
さらに東京は医療・介護資源が豊富なので、柴垣医院さんのように知名度があるのであれば簡単かと思います。あとはやるだけですね。一回始まればあっという間に広がりますから。
大西: ネットワークを作る上で情報がすごく強みになりますよね。例えば、「柴垣医院でこんなことを始めるみたいね」などという情報は、東京は回りやすいエリアだと思います。
柴垣先生としては、どうしていこうかというのはありますか。地域の訪問看護師さんに「私たちはPDをやるのでちょっと協力してくれませんか」と、言いふらせば良いでしょうか。
柴垣先生: そうですね。それも必要です。また勉強会を地域でやるとかもありますね。松本先生はそういうことやられていましたか?
松本先生: やっていましたね。勉強会で呼ばれると、例えば福岡に行くし、九州全域や東京にも行きます。実績が伴ってくると逆に今度は沖縄から見学にいらっしゃったりします。
柴垣先生: 今後、ADL(日常生活動作)が落ちた透析患者さんが都内では下手すると難民化してしまう可能性があります。それに対する受け皿が今のところあまりないのです。
大西: その受け皿になるのが今回の在宅でありPDであるかと思います。
今日また勉強させていただいたのが、在支診・在支病が受け皿ではないなと私は感じました。その枠組みにとらわれてしまうと診療報酬の波にのまれやすいですね。
大事なことは何かというと、患者さんが必要な医療をどう効率よく提供するのかということかと思います。点が何点になるか、ということは後からついてくる可能性があります。
今日、松本先生とお話した時に、必要があれば1回でも2回でも3回でも4回でも月に患者さんのところへ訪問すると聞きました。逆に1回で充分の方には1回しか行かない、と。
これは厚労省の考え方と少し異なりますね。厚労省は「最低2回」という言い方します。最低2回やるとこれだけ点数が取れます、逆に行き過ぎたら減算します、という考えです。これは利用者目線ではなく、医療提供側の目線ですよね。
でも、利用者さんは何回でも来てほしいい場合があると思います。そういうことを考えると、今のところCKD(慢性腎臓病)に関しては、腹膜透析は管理料がきっちり付いているため、ある意味自由度が高く行きやすいものではないかと思います。ただし医療保険に限りますが。
柴垣先生: 介護保険は使いづらいですね。
大西: 松本先生がおっしゃっていたように、「じゃあ、医療保険を使えばいいじゃない。介護保険届けしなければいいじゃない」というのも、訪問看護に関しては一つのやり方かなと思います。
柴垣先生: 生活面で介護保険も本当は使いたい場面もあるかもしれませんけどね。
益満さん: 生活介護に関してどういうことを望むかということですよね。役所に質問すると、生活支援で動いてくれる人色々な情報を教えてくれたりします。シルバー人材で安いところがあり、ワンコインで30分くらい片付けをしてくれるところがあるなど教えてくれたりします。
そのようなサービスを利用する場合は、介護保険を利用する必要はありません。どういうことをメインで介護保険を申請しようとしているのか、ということを、まずは関係者で論議して、そこからじっくり考えて介護保険申請する必要があると思います。
要介護状態でも、1日に2回毎日訪問看護を利用しようと思うと、月30万円以上の利用料金がかかります。その場合、要介護4くらいないと訪問看護師さんに朝夕入ってもらうことはできません。
医療保険での利用であれば、患者さんの負担を少なくして、一万円などとして、それも返ってくる形とすることができます。そのような方法をうまく使い、重心医療によって一日3回、毎日訪問看護を利用することができます。
柴垣先生: 永続的に医療保険を使えるわけではないですよね?
松本先生: 使えますよ。該当していればですね。
益満さん: どうしても施設に入らないといけない、などの条件に該当していれば大丈夫です。
松本先生: 施設の話をすると、施設にはたいていケアワーカーさんがいて、施設に入った後にどのような制度を使い、どのようなサービスを受ければ良いのか、ということをしっかり考えて教えてくれます。彼らはとても詳しいです。
そのような方々の話を聞いて、家族間で話し合い決めれば良いと思います。
逆に、そのようなことが分からずに患者さんを受け入れられない施設は、これから潰れますよ。そのような知識もなく、分からないから受け入れを断るような施設には、私達も頼みません。
大西: 例えば、利用者さんが施設に入るに当たり、「施設で腹膜透析をやりたい」と柴垣先生に相談したとしましょう。そうなると、柴垣先生は、導入施設を紹介し、腹膜透析を導入してあげて、サポートに入るという、作業が必要になるかと思います。
この流れを作るためには、やはり施設教育から行う必要がありますね。「施設でやれるんだ」と伝えていく必要があると思います。
「やれない」という施設は、松本先生がおっしゃる通り、単価の安い人しか受け入れられなくなりますね。
松本先生: 潰れますね、そういうところは。
大西: そのようなことを考えると、医療のスペシャリティの高い人、特別な人ほど、施設を見ていかなければならないですね。そして、伝搬者のように教えていくのが柴垣先生の役割であったり、いずれは東京モデルとなるのでしょうね。
松本先生: そうですね。そしてその時に大事なことがあります。私達医療者側からすると、そのような良い施設は、サバイブしてもらわないと困ります。頑張りすぎたりして、潰れてしまっては困るのです。
そのため、私達からもできることを行っていく必要があります。例えば、タイムリーに特別指示書を書くということです。そうすると施設の看護師だけでなくて、訪問看護が入れます。
それからもし区分変更が必要になったら、タイムリーに私達がすぐ対応してあげます。そういうことをすることにより、介護老人施設も経営が安定します。
私達からできることを一緒に提案して、やっていくことが大事です。
大西: ここで、今日、もう一つ、働き方改革について話したいと思います。医療現場での医師の働き方改革が2024年からスタートしました。
働き方改革というのは、残業してはいけないとか、有給休暇を取らなければいけない、ということだけではなく、柔軟な働き方を認める社会を作る試みだと思います。松本先生と益満さんは、それを地で行っているように感じます。
益満さん: 私自身はトリプルワークになります。メイン業務として病院で働いていて、PDの導入や手術などを行っています。
それから在宅のケアとして、訪問看護師さんたちの所に行けるように、あおぞらケアグループに所属していて、そこからPDの件も含めて行くような形を取っています。
そして、あおぞらケアグループ以外の訪問看護師さんを助けるために、まつもとクリニックから対応ができるような形としています。
このような形態はやはり大きな病院ではできないことで、唯一クリニックの看護師さんができる働き方だと思います。ですから、そのような看護師さんが柴垣先生の所にいらっしゃれば、もう少し柔軟に色々なことができるのではないかなと思います。
大西: 今日お話を聞いて来ましたが、色々な所に益満さんが登場してきます。それはどういうことかというと、松本先生がやることに全部関わるように考えていった結果、こうなったわけですね。
松本先生自体が病院に縛られない働き方をしているので、それをお手本として動いた結果かと思います。
これからの医師の働き方改革というのは、本当はここを改革するのが面白いのかなと思います。病院と医療従事者の契約を対等にするわけです。雇われるのではなく、「私はプロなのでこういう契約をしてください、いくらください、副業もします」というような形です。
その代わり全部が繋がっている状態を作れます。例えば、PDで繋がっている社会です。
松本先生: 分かりやすいですよね。
益満さん: 全く違う職種の仕事をするのではなくて、PDの患者さんのために、PDのナースを育てるために、地域に出て働いて、尚かつ自分に報酬が入ってくる、という形です。
大西: 益満さんそのものが地域包括ケアということですね。
柴垣先生: そういうことですよね。ある時はここ、ある時はあちら、と動き、これらが全部、地域包括ケアとしてつながっています。
大西: そうすると、益満さんのような方を地域に配置していくことによって、また新しい絵が描けるのではないかなと感じました。