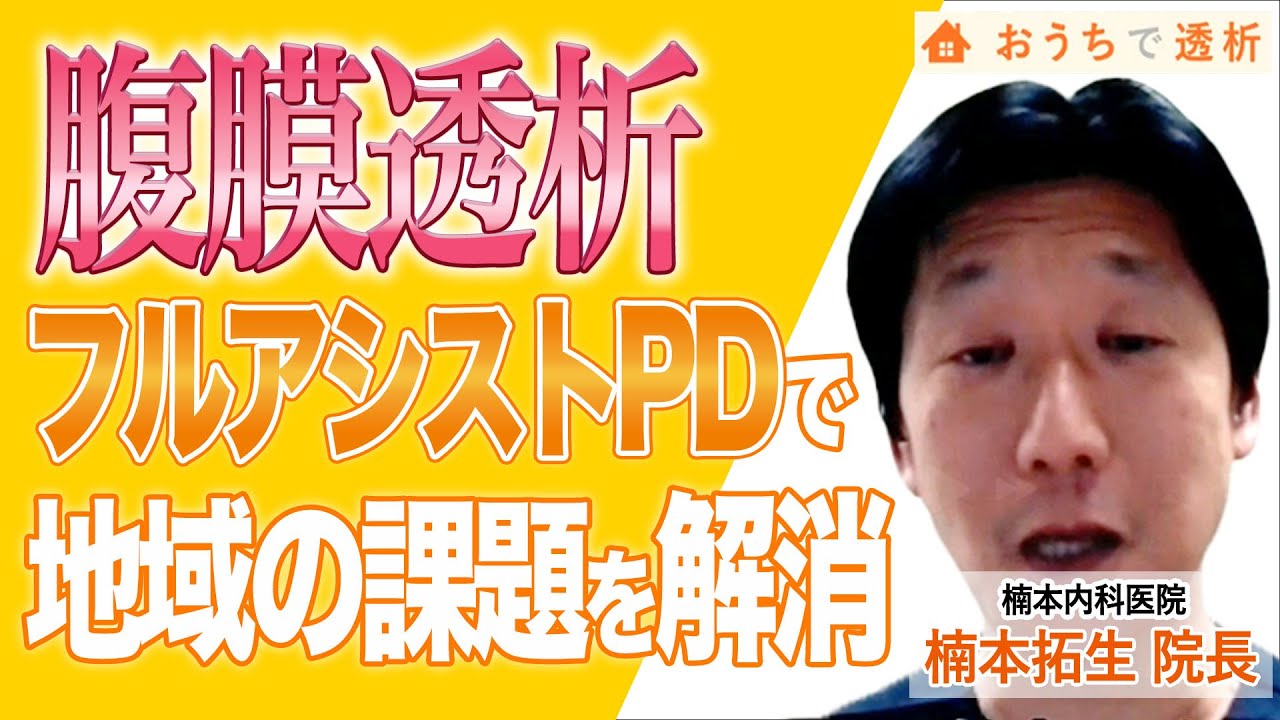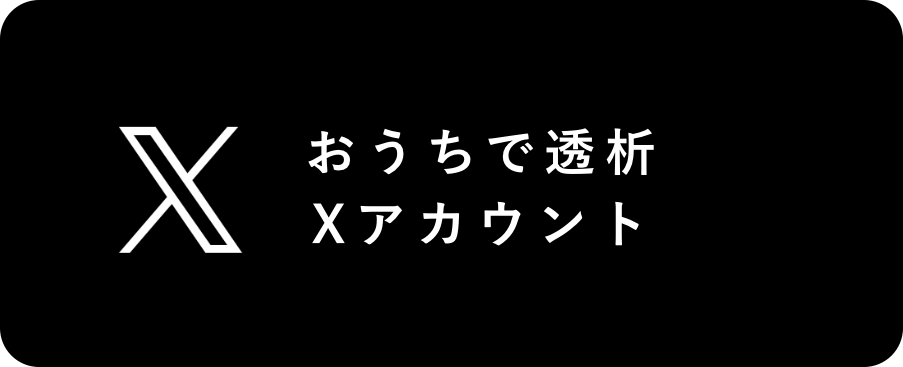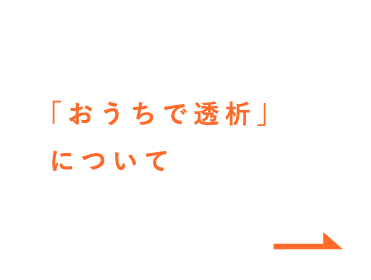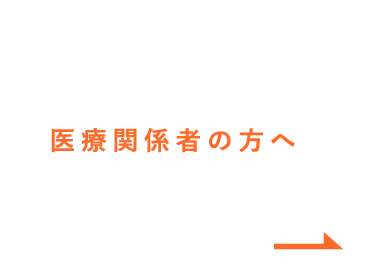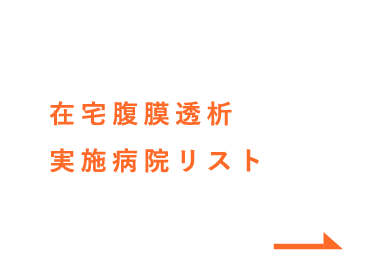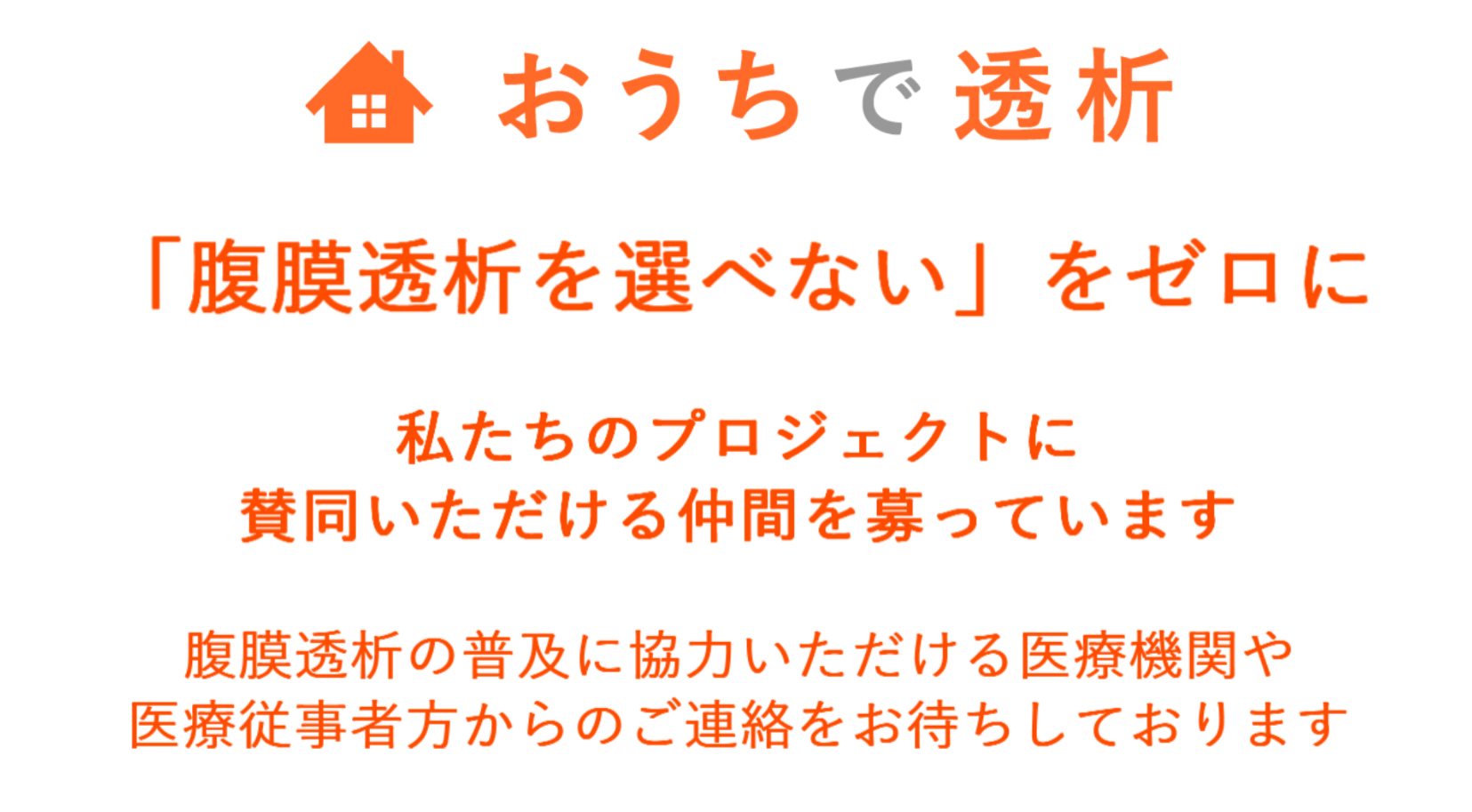楠本先生インタビュー①「腹膜透析」と出会ったきっかけ


楠本先生インタビュー①「腹膜透析」と出会ったきっかけ
文字サイズ
楠本先生インタビュー①「腹膜透析」と出会ったきっかけ
[楠本先生インタビュー①「腹膜透析」と出会ったきっかけ]
- 楠本内科医院(福岡県水巻町) 院長 楠本 拓生 様
聞き手:
- 医療コンサルタント 大西 大輔(MICTコンサルティング株式会社 代表取締役)
- 医療法人明洋会 理事長 柴垣 圭吾 様
大西: 本日は、楠本内科医院の楠本院長にお話を伺います。よろしくお願いいたします。まず、クリニックのご紹介からお願いできますでしょうか。
楠本先生: 当院は福岡県遠賀郡水巻町に位置し、北九州市に隣接した高齢化の進む地域にあります。1947年(昭和22年)に開院し、私が2016年に3代目の院長として就任しました。今年で開院77年目を迎え、院長交代後8年目となります。
当院は地域密着型のクリニックとして、私が継承してからは外来診療だけでなく在宅支援診療所としての機能も強化してきました。訪問診療にも積極的に取り組み、現在は約100名前後の患者さんを診ています。また、年間の看取り件数は40名前後です。
大西: 楠本先生が腹膜透析(PD)と出会ったきっかけは、どのようなことだったのでしょうか。
楠本先生: 私は久留米大学を2000年に卒業し、その後大学病院で勤務していました。医師6年目頃、当時の上司が血液透析クリニックの開業を予定しており、その際に「腹膜透析外来を任せたい」と言われたことがきっかけです。
自分から積極的に始めたというより、任された以上はしっかり学ばなければならないと思い、腹膜透析の勉強を始めました。
その頃、PDメーカーの紹介でTRC(トータルリーナルケア)研修に2泊3日で参加し、現在は日赤医療センターにおられる石橋由孝先生から熱い講義を受けました。
腎不全患者さんに対する全人的医療や、臨床心理学を取り入れた外来のあり方、さらには当時まだ珍しかった「退院前カンファレンスに地域の関係者を招く取り組み」などを初めて目にし、大きな感銘を受けました。
また、血液透析クリニックで高齢のPD患者さんを積極的に受け入れている現場を間近で見たことで、それまでの自分のPDに対する考え方が大きく変わりました。「これを大学に持ち帰ってしっかり取り組まなければならない」と強く感じたのです。
大西: 大学での取り組みを、クリニックを継がれた際にも始められたのでしょうか。
楠本先生: はい、そうです。大学での取り組みについて少し詳しくお話しします。
当時、PD患者さんは年間2〜3人程度で、主治医を担当する機会もほとんどありませんでした。そこで、私が学んだことを医局に還元したいと考え、「PD患者を増やしたい」と宣言しました。
実際に、療法選択の説明を患者さんやご家族に対して私自身が行うことから始めました。外来担当医は忙しく、看護師の協力も当初は得られなかったため、自分で患者さんを呼び、自分で丁寧に説明するというところからのスタートでした。
そのような活動を続けているうちに、病棟の看護師や透析室の看護師が徐々に手伝ってくれるようになり、院内の栄養士やソーシャルワーカーも協力してくれるようになりました。PD導入患者さんが増えるにつれて、多職種連携が院内に広がっていったのです。