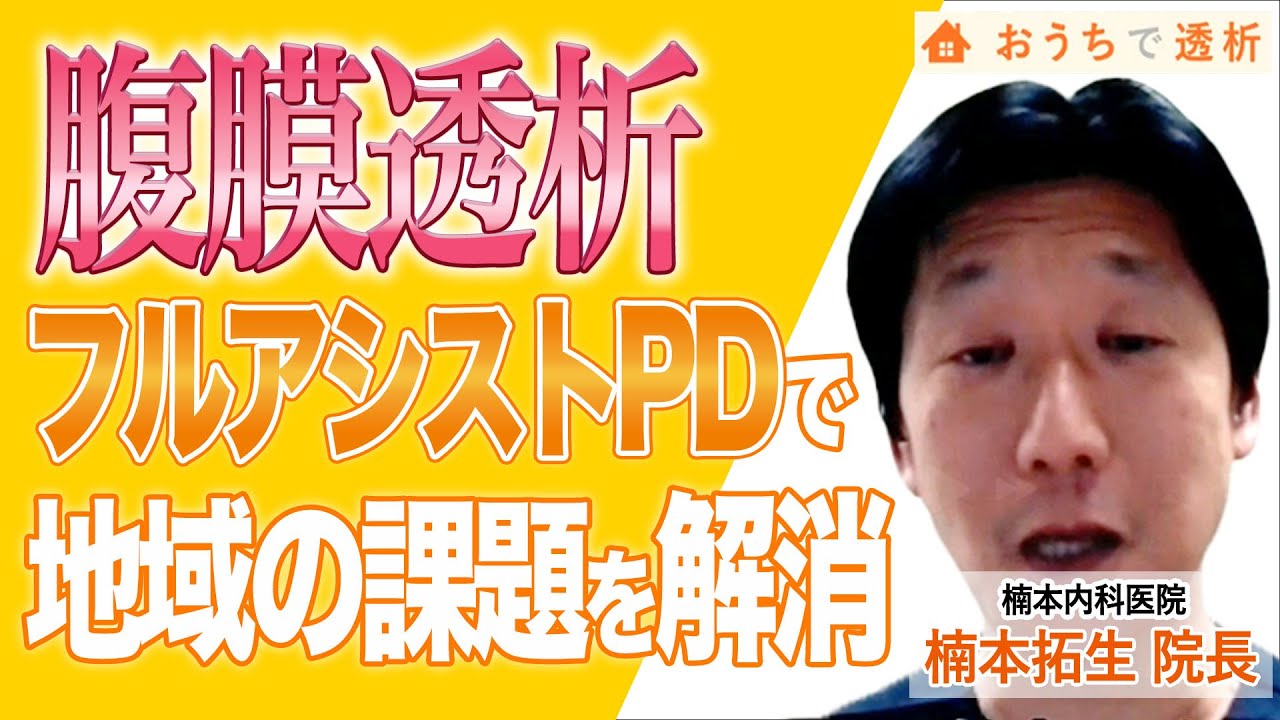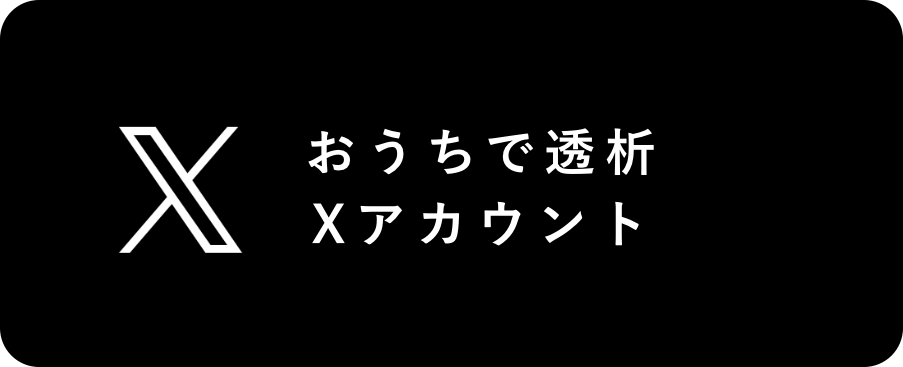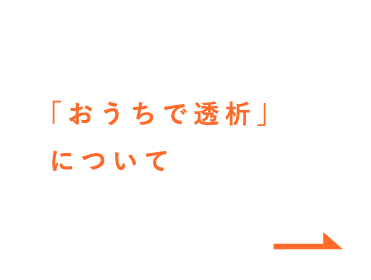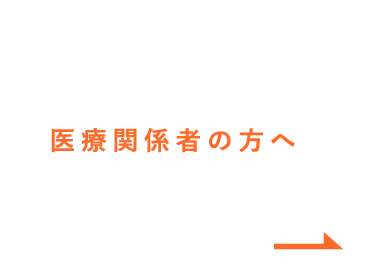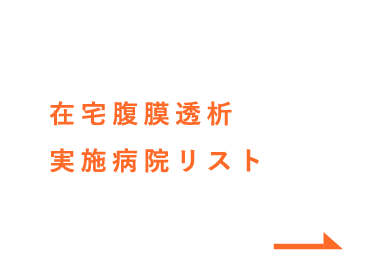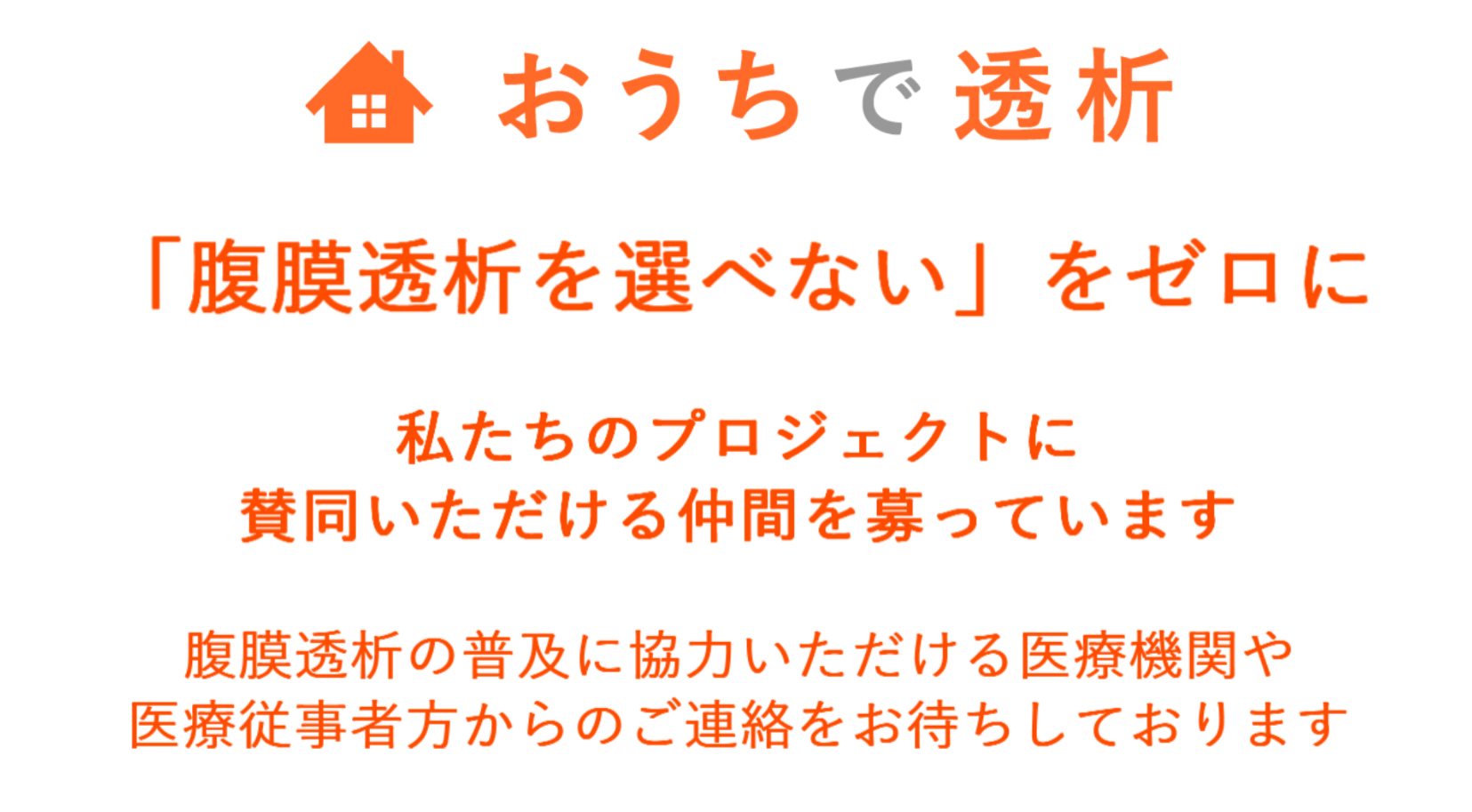楠本先生インタビュー②訪問看護ステーションにおける腹膜透析


楠本先生インタビュー②訪問看護ステーションにおける腹膜透析
文字サイズ
楠本先生インタビュー②訪問看護ステーションにおける腹膜透析
[楠本先生インタビュー②訪問看護ステーションにおける腹膜透析]
- 楠本内科医院(福岡県水巻町) 院長 楠本 拓生 様
聞き手:
- 医療コンサルタント 大西 大輔(MICTコンサルティング株式会社 代表取締役)
- 医療法人明洋会 理事長 柴垣 圭吾 様
楠本先生: 大学では、腹膜透析(PD)に関わる体制づくりを進めました。まず、PD患者さんを対象にしたカンファレンスを開いたり、独自の回診を行ったりして、後輩たちも巻き込みながら大学内で組織を作っていきました。
院内に多職種チームが形成され、連携がしやすくなり、ソーシャルワーカーも協力してくれるようになったので、次は地域に広げていこうと考え、訪問看護ステーションの開拓活動を始めました。
その過程で感じたのは、訪問看護に対していくら勉強会を行い、導入をお願いしても、PD患者さんは数年すると血液透析(HD)に移行してしまい、結果的に患者さんがゼロに戻ってしまうということです。これを繰り返すのは非常にもったいないと感じました。
そこで発想を変え、「高齢で自分で管理が難しい人だけが訪問看護を利用する」という従来の考え方から脱却しました。
腹膜透析は本来在宅医療であり、若い人であっても家の環境整備や導入期の不安を考えれば、一時的に訪問看護を利用してもよいのではないかと考えたのです。そこで、PD患者は全員訪問看護を導入するという取り組みを始めました。
その結果、年間20人前後のPD導入が行われるようになり、さまざまな訪問看護ステーションがPDに関わる機会を持ち、スキルアップにもつながりました。
質問や相談も増えてきたため、2か月に1度「PD連携カンファレンス」を開催し、関係者が顔を合わせて議論できる体制を整えていきました。
こうした取り組みにより、腹膜炎や出口部感染も減少し、訪問看護側のスキル向上による早期発見・早期治療が実現したと考えています。
大西: 久留米大学を中心にネットワークを構築してこられたわけですが、その中で最も苦労したことは何でしたか?
楠本先生: 最初は、訪問看護ステーションを探すこと自体が大変でした。当時、PDに対応できるステーションがほぼ存在しなかったため、地域で最も規模の大きいステーションに直接お願いに行き、「ぜひ協力してほしい」と頭を下げました。
また、自らいろいろな施設に足を運ぶようにしました。
PDが一般的ではなく、「PDとは何か?」という段階からのスタートだったため、どの施設も最初は恐る恐るという状況でした。そこで、一軒一軒直接訪問し、丁寧に説明し、導入をお願いするという地道な活動を続けました。
患者さんが増えればステーションも積極的に関わってくれるようになりますし、「この先生は本気で取り組んでいる」という熱意が伝わることが何より重要でした。諦めずに続けたことが成果につながったと思います。
大西: ドクター自身の「本気度」が重要なのですね。先日の鹿児島・松本先生のインタビューでも、先生ご自身が走り回って一軒一軒口説いて回ったとおっしゃっていました。やはりそうした姿勢が大切なのですね。
楠本先生: やはりそうだと思います。誰かに代理で行ってもらうのではなく、当事者である自分が直接足を運び、依頼することが最も気持ちが伝わる方法だと考えています。
大西: 久留米大学で築き上げた体制を、今度はクリニックを中心に、しかも北九州近くという別エリアで再構築していくわけですよね。クリニックに戻られてからの取り組みについて教えてください。
楠本先生: クリニックに戻ったときは、まさにゼロからのスタートでした。
久留米での経験を北九州でも活かしたいと考え、まずは自分が保存期から診ていた患者さんにPDを導入したことから始まりました。自分で説明し、基幹病院にカテーテル留置を依頼し、患者さんを戻してもらうという流れです。
その患者さんに訪問看護を導入する際には、「出口部はこのように洗浄します」といった具体的な指導を細かく行いました。
大学では看護師同士で指導し合う体制が整っていましたが、クリニックの看護師はPDを見たことがなく、私自身がすべて教える必要がありました。出口部の洗浄方法やトラブル時の対応などを診察中に訪問看護師と一緒に確認し、説明していきました。
こうした取り組みを積み重ね、一例一例増やしていくことから、クリニックでのPD体制づくりをスタートさせました。