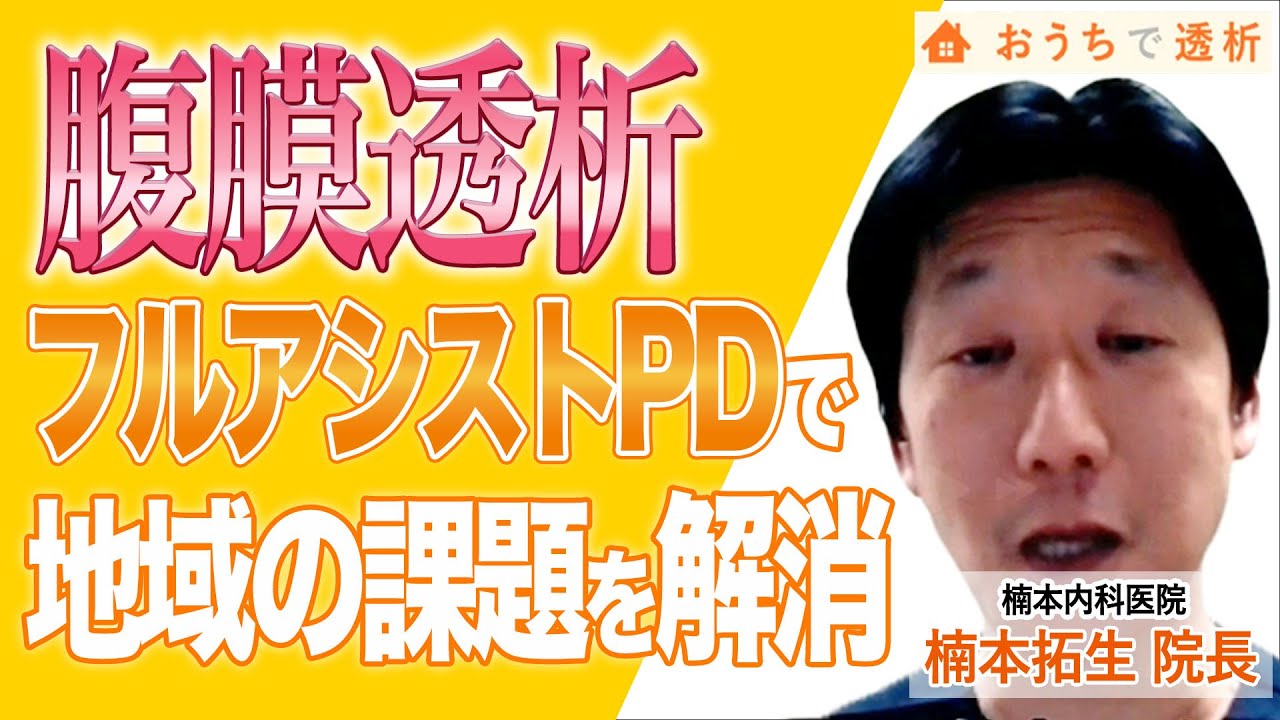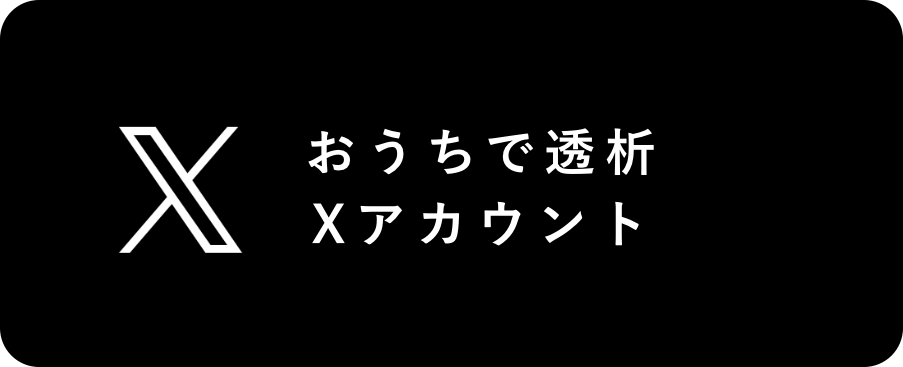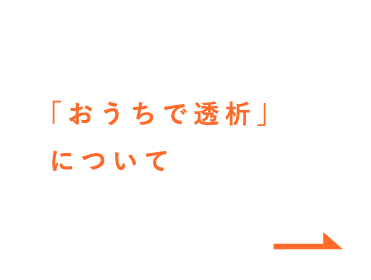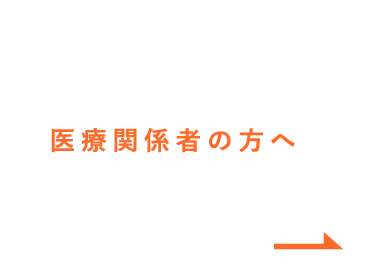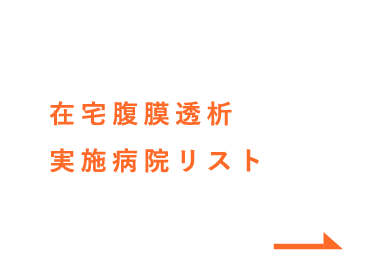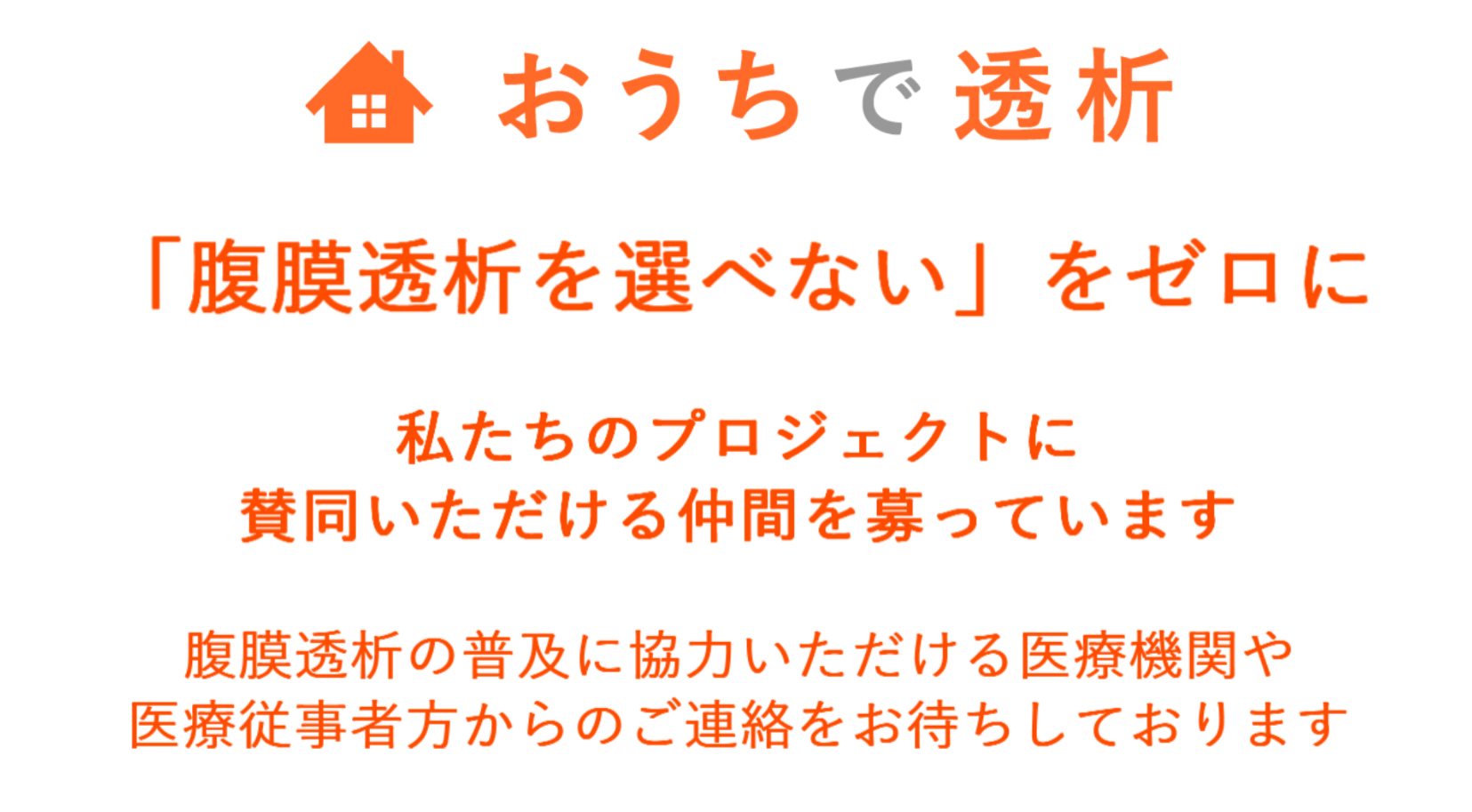松本先生インタビュー④なぜ腹膜で透析ができるのか〜透析治療の歴史〜


松本先生インタビュー④なぜ腹膜で透析ができるのか〜透析治療の歴史〜
文字サイズ
松本先生インタビュー④なぜ腹膜で透析ができるのか〜透析治療の歴史〜
[松本先生インタビュー④なぜ腹膜で透析ができるのか〜透析治療の歴史〜]
- 川原腎・泌尿器科クリニック(鹿児島県姶良市)
腎不全外科科長・腹膜透析センター長
松本 秀一朗 様
聞き手:
- 医療コンサルタント 大西 大輔(MICTコンサルティング株式会社 代表取締役)
- 医療法人明洋会 理事長 柴垣 圭吾 様
大西: なぜ日本では腹膜透析が普及しないのか、腹膜透析というものが広がっていないのか、ということに関して、先生のお考えをお聞かせください。
松本先生: まず腹膜透析の基本知識についてお話します。透析医療では腹膜と血液とありますが、やっていることは基本的に同じで、人工的に血液中の余分な水分や老廃物を取り除いて血液をきれいにしています。
透析で除去する物質というのは、小分子物質というのですが、これは透析で抜くことができます。半透膜という昔理科で習った原理です。血液細胞は抜けないが、小分子は抜けるというその原理を使って、毒素を抜いたり水分を抜いたりするということになります。
人類で初めて臨床で行ったのは、1923年に行ったガンター先生です。そして初めて命を助けることができたのは1946年と言われています。
偶然ですが血液透析のコルフ先生の人工腎臓の成功とほぼ同時期です。コルフ先生は元々オランダ人で、第二次世界大戦中はナチスの管理下のオランダで研究していました。能勢先生の話だと、1944年ぐらいには成功していたらしいです。
ナチスの業績にされるのを嫌がって1945年とか6年に発表されたと言っていました。彼はその後アメリカに移りました。当時は大掛かりな機械で、ドラム式の血液透析などを行っていた時代がありました。大がかりなので、多くの患者さんは救えません。
血液透析が認められたきっかけは朝鮮戦争でした。朝鮮戦争でアメリカ兵が瓦礫の下敷きになったりして、腎不全になり、当初は死亡率90%ぐらいでほとんど亡くなっていました。クラッシュシンドロームですね。
そこで、この血液透析の機械を使うことで、死亡率がなんと50%まで改善したということで、アメリカ軍が莫大な資金を提供することになりました。当時アメリカは朝鮮戦争のために、沖縄キャンプか福岡キャンプに傷病兵を運んできて腎不全治療をしました。
偶然ですが、九州大学の澤田内科の先生たちが、その福岡キャンプで対応しているドクターの話を聞いて、これはすごい治療になっているということで、日本で初めて九州大学で人工透析の機械を輸入して始めた、というのが日本でのきっかけです。
人工腎臓が広がるきっかけの頃、ちょうど日本もそういうものに接する機会があったのです。
腹膜透析に関して言うと、国内での初めての救命は1956年で、当時長崎大学の泌尿器科にいらっしゃった城代先生の例とのことです。
患者さんも外科の先生で、天草の先生らしいのですが、貝を食べて貝毒で急性腎不全になり、たまたま知り合いを伝って、大学で研究していた城代先生を頼ってきて、急性腎不全を乗り切った、というのが日本で初めての救命例だそうです。
その後、透析医療は効果があるということで、腎不全の患者さんがみな受けたいとなったわけです。
けれども提供できる台数が限られていました。
僕ら医学部の臨床倫理で必ず習う話なのですが、1962年のシアトル(米国)では、神の委員会と呼ばれている有識者たちが「若い患者さんで、そして社会的価値のある人で、治療して助ける価値のある人」を選別して治療を提供してきた、という経緯があります。
全員が生きられない時に誰が生きれば良いか、という問題です。これはまさに日本でコロナ禍の中で、透析患者さんが直面した問題でした。透析が始まる頃も、そういう問題があったわけです。
その6年後ぐらいの日本の状況はどうだったかというと、今の透析医学会の前身である「人工透析研究会」で、第2回に千葉大学の先生が統計を取られています。
この頃は一週間で透析できる日本の患者さんの数は400人から500人ぐらいです。今思うと考えられない数です。これくらいの患者さんに対してしか透析できなかったのです。
その後、血液透析においては内シャントの開発やホローファイバー型のダイアライザーが開発されました。腹膜透析においてはカテーテル、皮下埋め込み型のテンコフカテーテルが開発されました。
それにより、慢性腎不全にも治療ができるポポビッチとモンクリフの理論、CAPDでの理論ができたことにより、それまで急性腎不全しか助けることができなかったものが、慢性腎不全の患者さんも助けることができるようになりました。
急性腎不全だけであれば、全国で数百人とか数千人の治療ができれば良かったのかもしれませんが、慢性腎不全までできるようになったので一気に広がりました。
1977年、日本は繊維不況に喘いでいて、今の旭化成や東レといった企業団がアメリカに視察団として行きました。写真の真ん中に座られているのは太田和夫先生です。その右側に向かって左にいらっしゃるのは柴垣先生のお父さんではないでしょうか。
人工臓器や腎移植の調査を行う中で、アメリカやカナダで腹膜透析がたくさん実施されていて、そして血液透析もどんどん増えていて、これは日本でも実施しなければならないし、ビジネスチャンスだと考えて、現在のダイアライザーを作っている会社などが中心になって、一気に実施し始めました。
林寺もこれをきっかけに腹膜のカテーテルをやり始めたと言っていました。
その後、腹膜透析に関しては腹膜炎の問題が出ましたが、それは紫外線照射自動接合装置によって劇的に減りました。