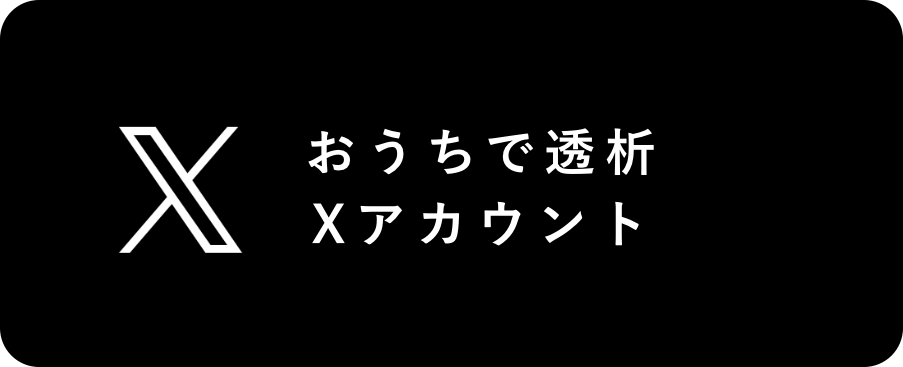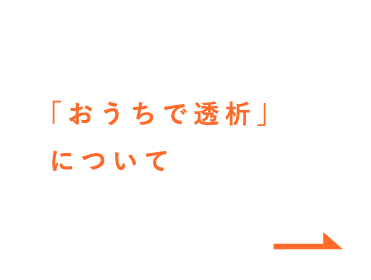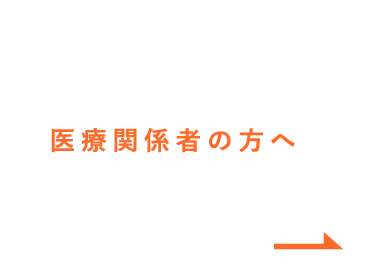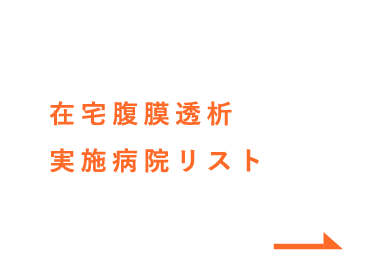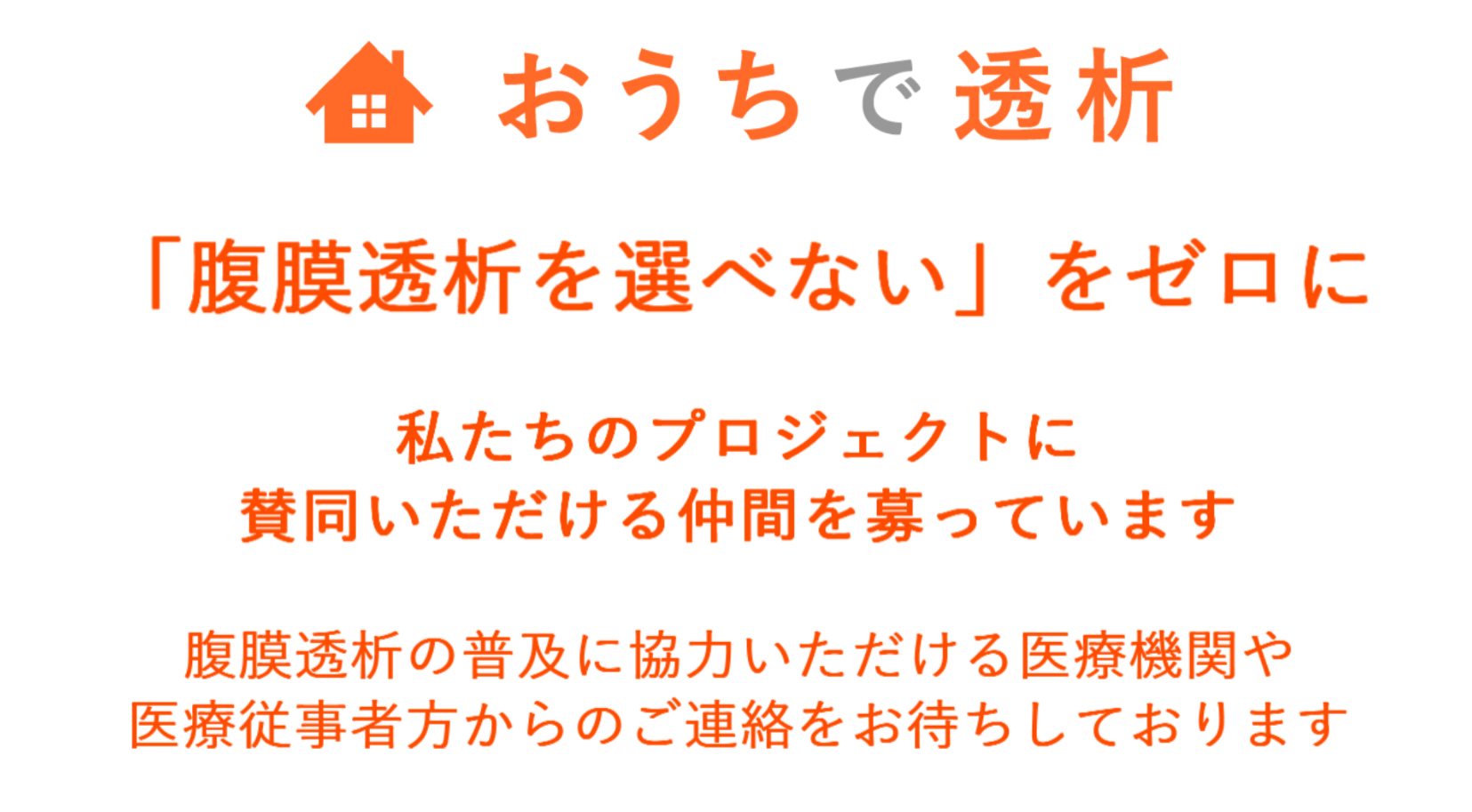松本先生インタビュー⑭終末期における腎代替療法の比較〜腹膜透析と地域連携〜


松本先生インタビュー⑭終末期における腎代替療法の比較〜腹膜透析と地域連携〜
文字サイズ
松本先生インタビュー⑭終末期における腎代替療法の比較〜腹膜透析と地域連携〜
[松本先生インタビュー⑭終末期における腎代替療法の比較〜腹膜透析と地域連携〜]
- 川原腎・泌尿器科クリニック(鹿児島県姶良市)
腎不全外科科長・腹膜透析センター長
松本 秀一朗 様
聞き手:
- 医療コンサルタント 大西 大輔(MICTコンサルティング株式会社 代表取締役)
- 医療法人明洋会 理事長 柴垣 圭吾 様
松本先生: 制度については少し複雑ですが、腹膜透析患者は「別表8」の扱いとなり、1日3回、最長90分まで訪問看護を受けることができます(そのうち1回はリハビリも可能)。1つの訪問看護ステーションで足りなければ、複数の事業所を利用することもできます。
また、身体障害者1級であれば医療費負担もありません。この制度を活用し、社会的入院を回避することを目指しています。
地域では、新たに腹膜透析を始めたいという病院があれば、私たちが支援に入り、教育や手術指導などを行ってきました。その結果、鹿児島では腹膜透析患者が2倍以上に増えました。
新規導入施設も、私たちが従来使っていた訪問看護ステーションなどを活用できます。これらは正に「社会的共通資本」として機能しています。私たちはこの10年、こうした活動を続けてきました。
私は鹿児島には全く知人がいない状態でゼロからスタートしました。ほんの一滴が落ちるように始まった取り組みでも、社会的に良いことはあっという間に広がるという好例だと思います。
パートナーとしては、あおぞらケアグループがあります。若い社長が「医療依存度の高い方を積極的に受け入れ、社会貢献の一環として取り組む」と賛同してくださり、腹膜透析についても非常に理解が深い企業です。
8年前、たった3人からスタートしましたが、今では常勤訪問看護師50名、腹膜透析患者35名という、国内最大規模の腹膜透析対応訪問看護ステーションにまで成長しました。彼らとは呼吸も合い、非常にスムーズに連携が取れています。
このように地域で信頼できるパートナーを見つけ、お互いに成長していくことが大切です。今では、在宅支援診療所、非透析病院、有料老人ホーム、看護小規模多機能型居宅介護、サービス付き高齢者住宅、特別養護老人ホームでも腹膜透析が行われています。
このようなネットワークを意識的に作るべきです。病院の中だけで完結させず、地域全体を意識し、社会的共通資本としてネットワークを活かしながら、地域と共に成長していく仕組みが必要なのです。
病院内の経営や病院内の人材だけに頼ろうとする考え方は、もう前に進みません。そういう考えはやめるべきです。
ちなみに、私は魚釣りが大好きで、車には腹膜透析の道具と釣り竿がごちゃ混ぜに積んであります。何かあればすぐ対応できるよう、ボーダーレスに仕事をしています。
ただし、普段私は仕事が速いので、朝8時半から夕方5時には必ず終わらせます。昼休みは1〜2時間取り、魚釣りに行くこともあります。天気が良ければ、夕方5時過ぎから釣りに行く毎日です。
社会的入院患者には、これまで30例ほど腹膜透析を導入しました。腹膜透析に変更すると、6〜7割の方が自宅に戻れています。社会的入院患者がそれだけ多いという現実もあります。そして、そのまま終末期まで診ることを目標にしています。社会的入院はさせません。
血液透析の場合、自宅での看取りはほぼ不可能です。最終的には透析中断=安楽死の判断が必要になり、集中治療室で亡くなる方も多いのが現実です。
しかし腹膜透析は元々在宅で行っているため、そのまま終末期について話し合い、「これが自然な流れです。苦しみがなければこのまま続けましょう」と説明できます。腹膜透析は中断の必要がなく、亡くなる前日まで比較的元気な方が多いです。
腹腔内にブドウ糖を入れていることも影響しているかもしれませんが、前日まで笑って食事をしている方も多く、穏やかな最期を迎えられます。安楽死の判断も不要です。
医療依存度が低いため、家族との信頼関係がしっかりしていれば、最期でも救急車を呼ばずに済む場合があります。仮に救急車を呼んでも、病院に搬送された際、事前にこちらから連絡し「この患者さんは家族と話し合い済みで、集中治療を希望していないので帰して良い」と伝えます。そうすれば病院側も助かります。
このように、地域内のネットワークで支えることが重要なのです。