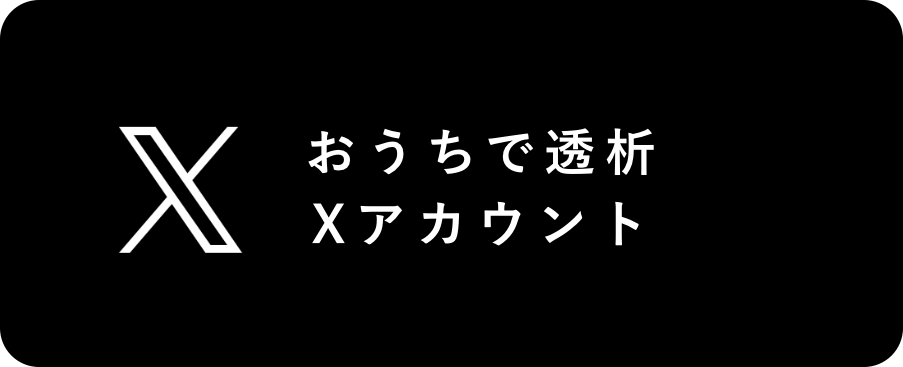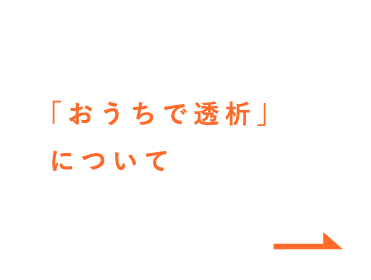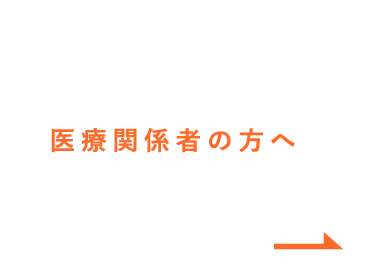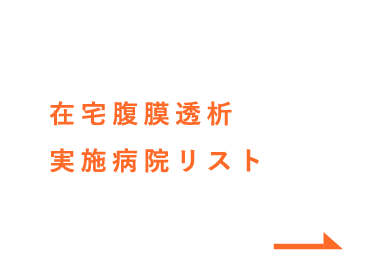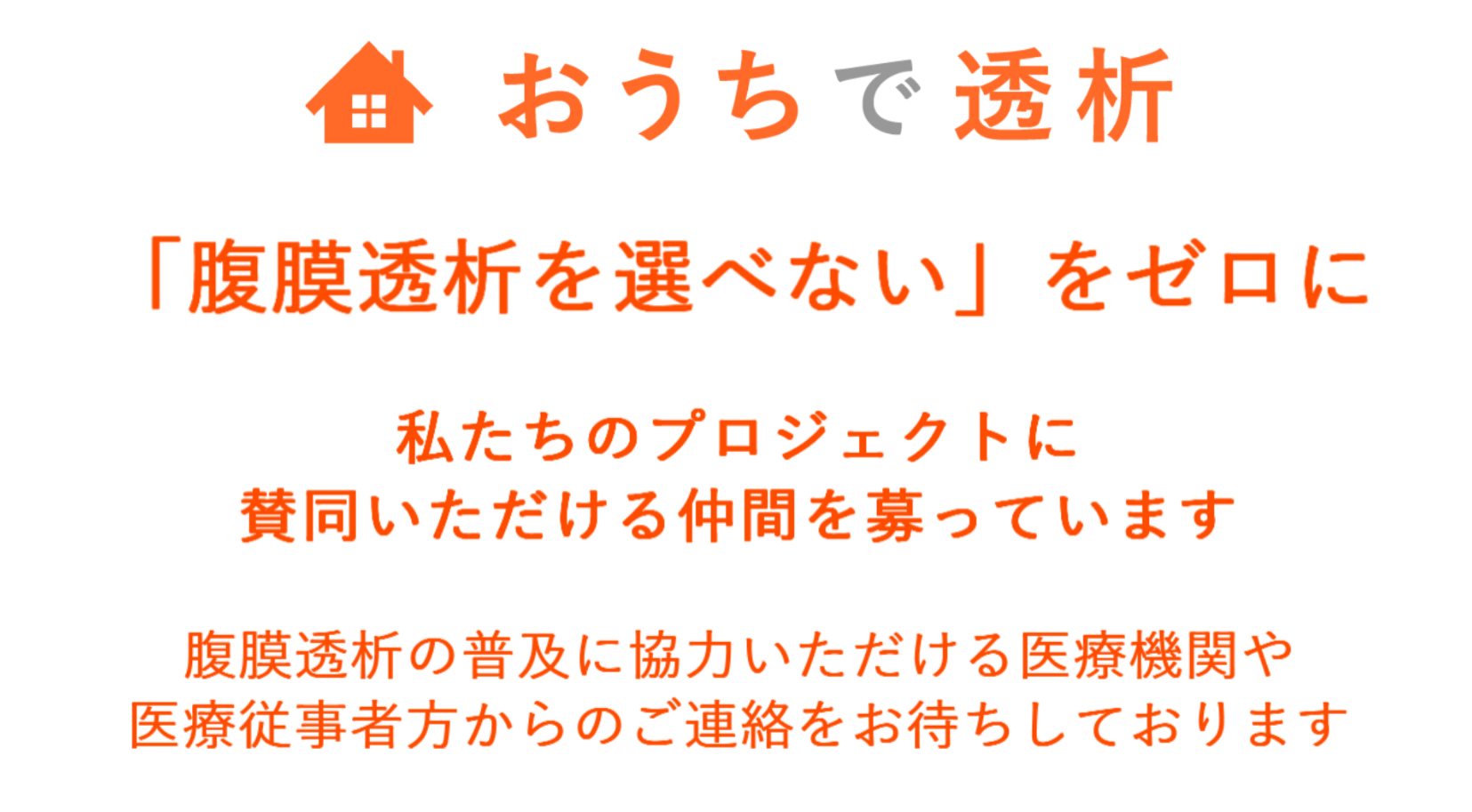松本先生インタビュー⑮不毛の地と言われた鹿児島〜腹膜透析プログラム成功の理由〜


松本先生インタビュー⑮不毛の地と言われた鹿児島〜腹膜透析プログラム成功の理由〜
文字サイズ
松本先生インタビュー⑮不毛の地と言われた鹿児島〜腹膜透析プログラム成功の理由〜
[松本先生インタビュー⑮不毛の地と言われた鹿児島〜腹膜透析プログラム成功の理由〜]
- 川原腎・泌尿器科クリニック(鹿児島県姶良市)
腎不全外科科長・腹膜透析センター長
松本 秀一朗 様
聞き手:
- 医療コンサルタント 大西 大輔(MICTコンサルティング株式会社 代表取締役)
- 医療法人明洋会 理事長 柴垣 圭吾 様
松本先生: 新型コロナの流行期には、患者さんが入院すると家族が面会できない状況が続きました。そのため、終末期の患者さんについては「在宅で看取りたい」という家族が増えてきました。これをきっかけに、3年前から腹膜透析の患者さんは、今では全例が在宅か施設で看取られています。
私自身はずっと外科医だったため、これまでは病院で看取ることが多く、以前は「透析患者さんは大変だから入院して看取ろう」と言って、入院させたこともありました。
しかし、この10年ほど初めて在宅での看取りに関わるようになり、現場を経験しました。そこで感じたのは、在宅の看取りは非常に穏やかで良いものだということです。病院ではないため余計なことをせず、静かに最期を迎えることができます。
私は、自分が勧めてきた腹膜透析という医療行為が本当に適切だったのかを、患者さんや家族の様子を見ながら「答え合わせ」するつもりで終末期に立ち会っています。それが医療者として非常に大切なことだと思っています。
最近では、腎代替療法の説明は病院で看護師が担当することが多いのですが、私は「その後どうなっているのか、患者さんを見に行った方がいい。できれば最後に亡くなるときも見に行った方がいい」と伝えています。
そうでなければ本当の説明はできない、と考えているからです。これは自分自身の経験から言えることです。私自身、経験していなかった頃は、本当の説明ができていなかったように思います。「知らない」というのはそういうことだと思います。
だからこそ、私はできる限り看取りにも立ち会うようにしています。
たちが「緩和的な腹膜透析」と呼んでいる方法では、社会的入院を回避でき、在宅療養が可能になり、患者さんも楽に過ごせます。そして最期を「上手に」迎えることができます。
日本は宗教的な儀式が少ないため、代わりに「演出」が必要ですが、医療者が「良かったね」と思えるような形をつくることが重要です。それは同時に自分自身へのグリーフケアにもなります。
これからは多くの患者さんが亡くなる時代になりますが、その都度心を痛めるだけでは続きません。「やってよかった」と思えることで次に繋げることができるのです。私はそのことを看護師たちにも伝えています。
「腹膜透析不毛」と言われていた鹿児島で、この10年間に国内有数の維持症例数まで増えたのには様々な背景があります。
一つはアンメットニーズ、つまり本来腹膜透析が適している患者さんが多いにもかかわらず、説明不足などにより血液透析が選ばれ、結果的に社会的入院となっているという現実です。そのような方々に腹膜透析という医療を知ってもらい、選んでもらえることが大切です。
YouTubeはその点で非常に有効です。実際にYouTubeでこうした話をすると全国から問い合わせがあり、鹿児島でも「病院の先生から説明を受けていないので診察を受けたい」と飛び込みで来て、腹膜透析を始める患者さんが多くいます。
いかに情報が患者さんや家族に届いていないか、ということが分かります。そして正確な情報を伝えることで正しい選択肢を選んでもらえるかが重要だということです。「終末期まで付き合います」と言えるのは、急性期病院ではなかなか難しい一言ですが、非常に大切です。
これが私が病院を辞めた理由の一つでもあります。小規模でフットワークの軽いクリニックの方が実践しやすいからです。院長に「こういうことをやりたい」と言えば「いいよ、やってごらん」とすぐに許可が出ます。
しかし病院では「昼間の患者はどうするの」「救急対応は誰がやるの」「当直はどうするの」といった意見が出て、結局できないことが多いのです。
私はそうした体質を「ばかげている」と感じていました。病院にいたときは医局会にも出ず、院長に呼ばれても無視しました。私は奴隷ではなく、一人の自立した医療者です。だからこそ「患者さんを中心に自分はどう動くべきか」を毎日考えながら取り組んでいます。
大西: 松本先生ありがとうございました。
「知らない」ということがいかに問題で、正しい情報を伝えることがこの腹膜透析を普及させるための近道であることが分かりました。
これから私達と一緒に腹膜透析を広げてくれる方がいらっしゃいましたら、またご連絡をいただければと思います。
改めてありがとうございました。