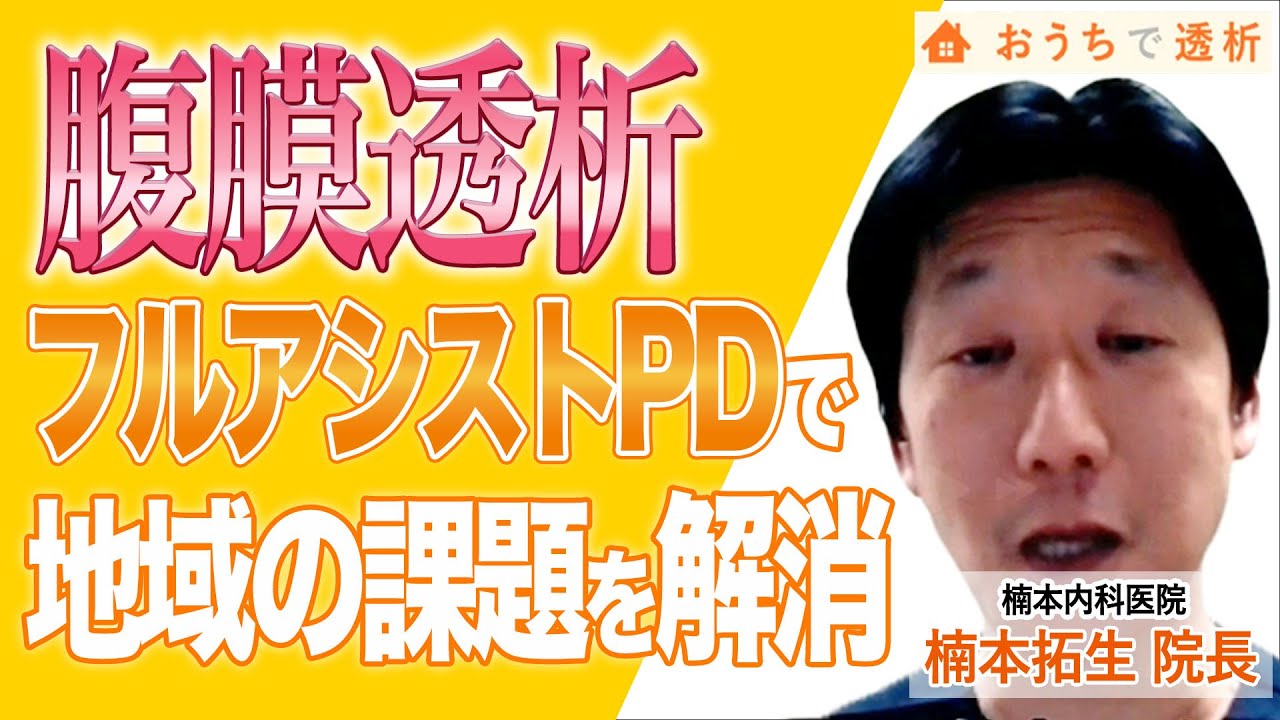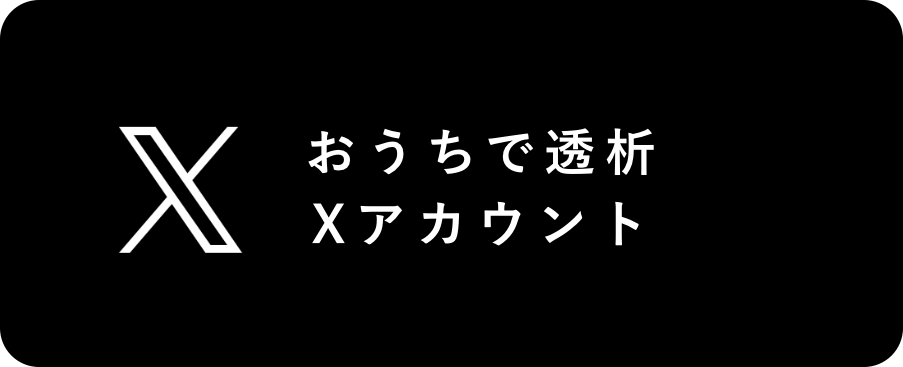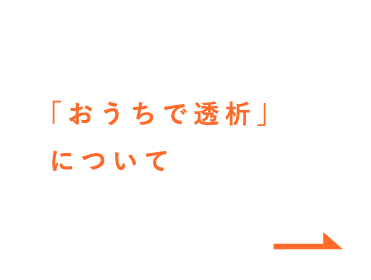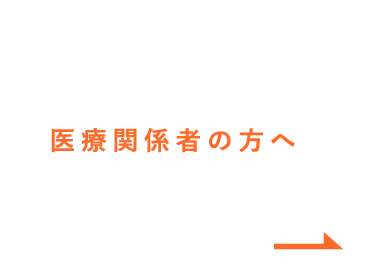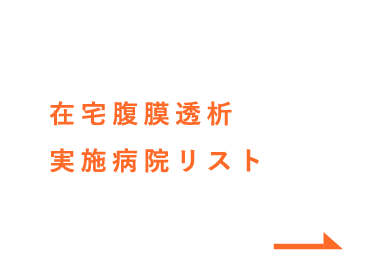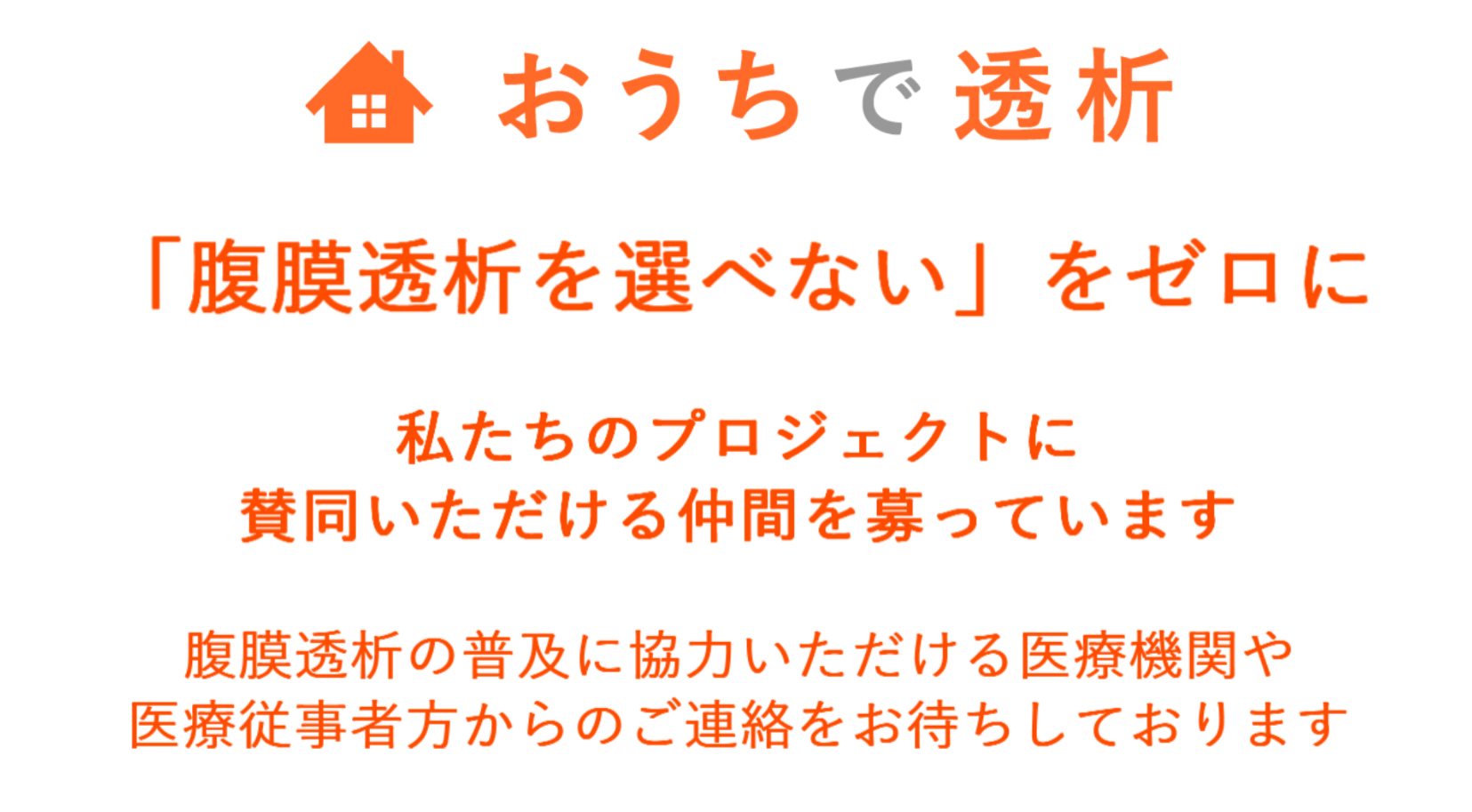腹膜透析鹿児島モデルインタビュー②


腹膜透析鹿児島モデルインタビュー②
文字サイズ
腹膜透析鹿児島モデルインタビュー②
[腹膜透析鹿児島モデルインタビュー②]
- 川原腎・泌尿器科クリニック(鹿児島県姶良市)
腎不全外科科長・腹膜透析センター長 松本 秀一朗 様
看護師 益満 美香 様
聞き手:
- 医療コンサルタント 大西 大輔(MICTコンサルティング株式会社 代表取締役)
- 医療法人明洋会 理事長 柴垣 圭吾 様
大西: 松本先生に質問です。PD(腹膜透析)が鹿児島でうまくいった理由はありますか。
松本先生: よく講演会でも話していますが、大きく分けていくつかの理由があります。
1. 時代的なニーズ
高齢化が現実のものとなり、高齢者にとって腎不全治療としての腹膜透析の価値は以前から高いと分かっていました。そのニーズが一層はっきりしてきたのです。
2. 地域包括ケアシステムの成熟
国が2000年に介護保険制度を始め、「地域包括ケアシステム」を進めるようになってから20年近く経ち、地域で「アシストPD」を受け入れる仕組みが完成してきました。
3. IoTの進歩
この20年で最も大きな進歩はIoTです。20年前には今のようなことはできませんでした。IoTと地域包括ケアネットが融合したことで、患者さんを受け入れる体制が整い、アシストPDが現実に可能となりました。その結果、自宅や施設でも「バーチャルホスピタル」のように、病院と同等、場合によってはそれ以上の質の高い医療を提供できる時代になりました。
4. 終末期医療への意識の変化
私自身は急性期医療や臓器移植に関わってきましたが、その中で欠けていたのは「人生の最も大事な終末期」でした。高齢者の透析は70〜80歳から始める方が多く、その終末期をどう支えるかを考えるようになったのがこの10年です。地域包括ケアシステムと組み合わせることで、社会的入院を避けながら地域で支えられる仕組みを作ることが可能になりました。
これは鹿児島だけの話ではなく、全国で普及できることです。皆さんにもぜひ挑戦していただきたいです。そのための協力は惜しみません。鹿児島に来ていただいたり、呼んでいただければ、私の経験をもとに協力します。
大西: 「まるで病院」という状況を作り出したのはICTだと思います。2000年代は携帯電話の時代でしたが、その後iモードやインターネットを経て、今はIoTが当たり前になりました。
その流れの中で大きなブレイクスルーが起きました。例えば、病院内の申し送りよりもはるかに高い質のコミュニケーションが可能になりました。それがメディカルケアステーションです。
松本先生がカルテを書かれる際、訪問看護師が得た情報をもとに入力しています。訪問看護師が「前さばき」をし、先生が「後ろさばき」をすることでうまく回るのです。
昔はFAXで対応しており、それでは限界がありました。地域包括ケアを目指すためにICTは不可欠であり、それが整うまでに20年かかったということですね。
松本先生: ICTと腹膜透析との親和性が非常に高いということですね。
大西: はい。24時間365日フォローする際には「記録だけ残しておく。後で対応する。」という考え方が重要です。リアルタイムでなくても、半日や数時間遅れても問題なく対応できることが重要です。次の日に対応する前提で、とりあえず状況だけ残せば良いのです。
以前は「大変だ、電話しなきゃ」でしたが、今は「後で対応できる」。これがITの力だと思います。先生、本日はありがとうございました。