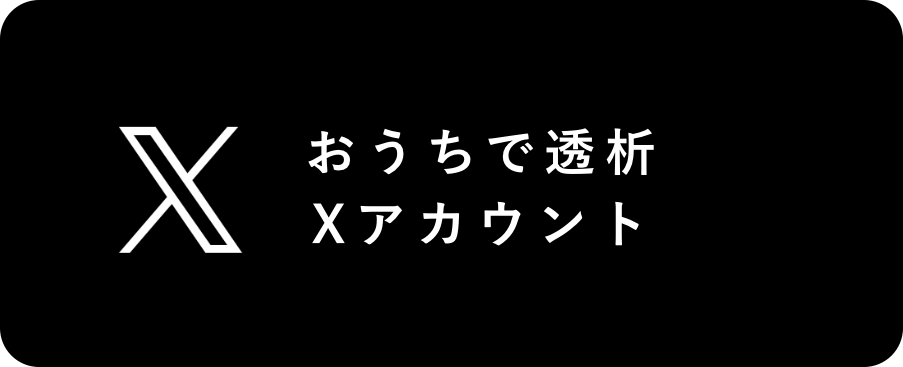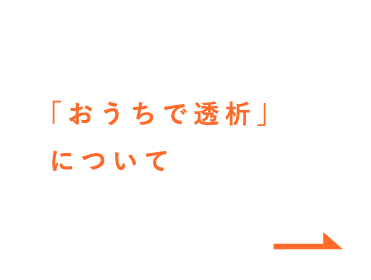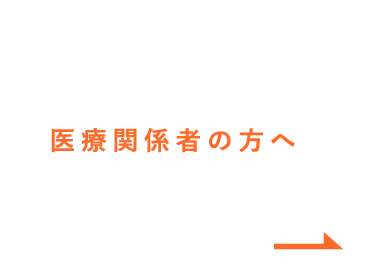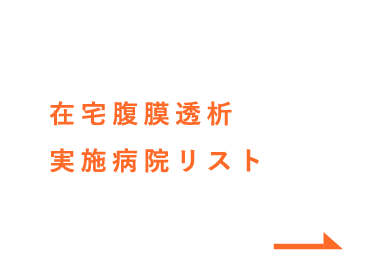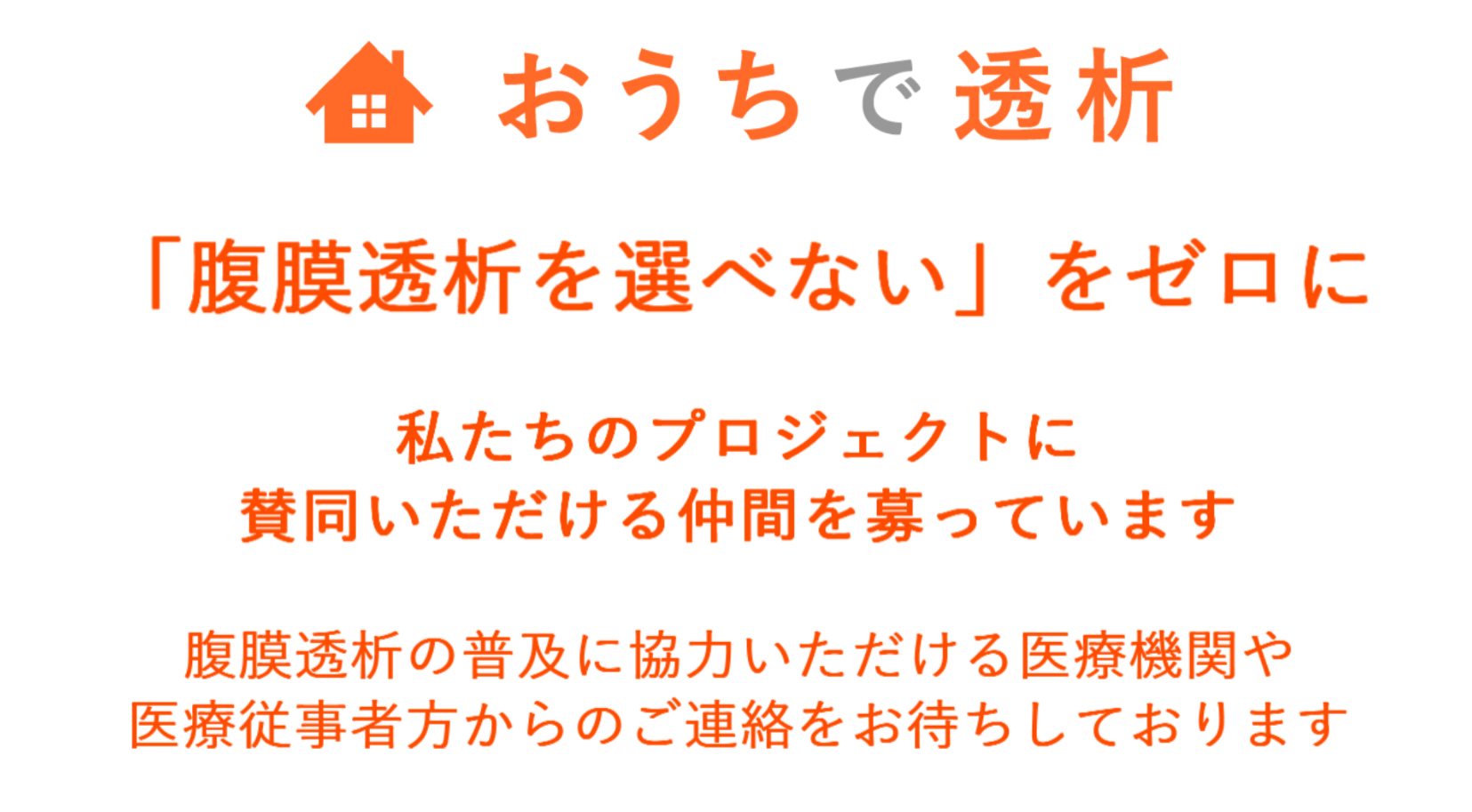腹膜透析鹿児島モデルインタビュー③「鹿児島モデル」に追いつくには?


腹膜透析鹿児島モデルインタビュー③「鹿児島モデル」に追いつくには?
文字サイズ
腹膜透析鹿児島モデルインタビュー③「鹿児島モデル」に追いつくには?
[腹膜透析鹿児島モデルインタビュー③]
- 川原腎・泌尿器科クリニック(鹿児島県姶良市)
腎不全外科科長・腹膜透析センター長 松本 秀一朗 様
看護師 益満 美香 様
聞き手:
- 医療コンサルタント 大西 大輔(MICTコンサルティング株式会社 代表取締役)
- 医療法人明洋会 理事長 柴垣 圭吾 様
大西: 柴垣先生、今日は松本先生に1日同行されましたが、そのご感想をお聞かせください。
柴垣先生: はい。松本先生からもお話がありましたように、この10年、20年で医療分野における大きな変化の一つは、IoT(Internet of Things:モノのインターネット)が実際に使えるようになったことだと思います。
しかし、私が東京で医療に携わっている中では、いまだにFAXや患者さん宅の連絡ノートを使ったコミュニケーションが中心です。
「どちらが進んでいるのか」と考えると、非常に複雑な気持ちになります。一般的には東京の方が進んでいるように思われますが、実際はまだFAXと紙のノートが現役です。
その意味では、今年こそが医療DXの元年だと感じました。東京も、この鹿児島モデルに一刻も早く追いつかなければならないと痛感しています。
大西: おっしゃる通りですね。都会だからといって、必ずしもITやIoTが進むわけではありません。結局のところ、「使う人が本当に必要だと感じるかどうか」が一番大きな影響を持っています。
社会全体が「FAXでいいや」「メールで十分」「手紙で済む」と思っている限り、変化は起こりません。だからこそ鹿児島モデルのように、「これ以外の手段は使ってはいけない」というようなルールをあえて作り、使わざるを得ない環境を整えたことが大きいと感じました。
要するに、「この方が絶対に便利だから、覚えればいいんだ」という強い動機づけが必要なのです。
実は、私自身も昔はITなんて無理だと思っていました。しかし、松本先生は「無理じゃない、無理って言うな」と情熱的に語りかけてくださった。その熱に突き動かされて、周囲の人たちがなんとか食らいついてきたんのだと思います。
だからこそ、「追いつくためには何をすればいいのか」と問われれば、答えはシンプルで、まず使ってみることです。使えばその便利さが分かります。
PDの普及においても、この「まず使ってみる」という姿勢こそが、最も大切だと思います。