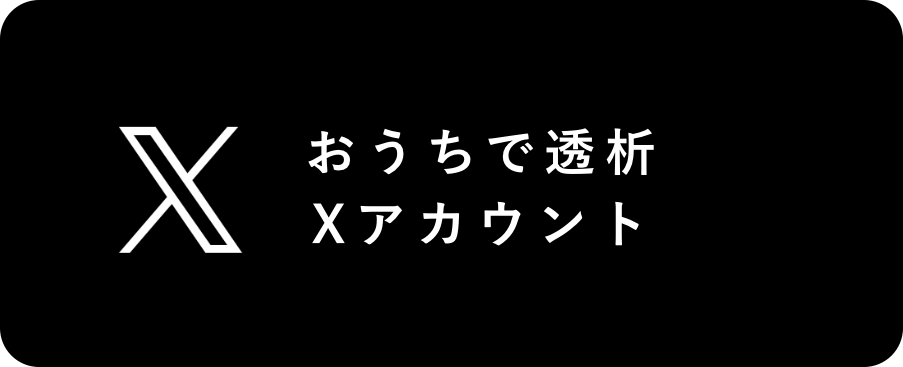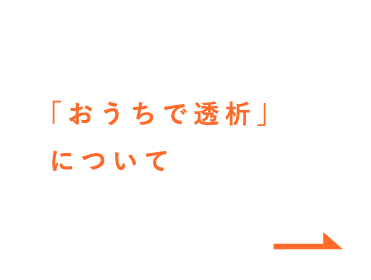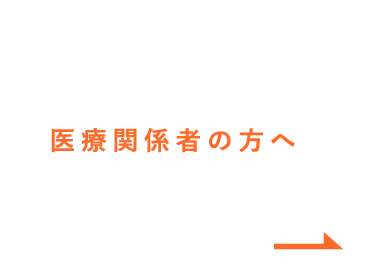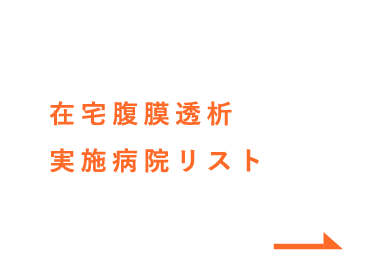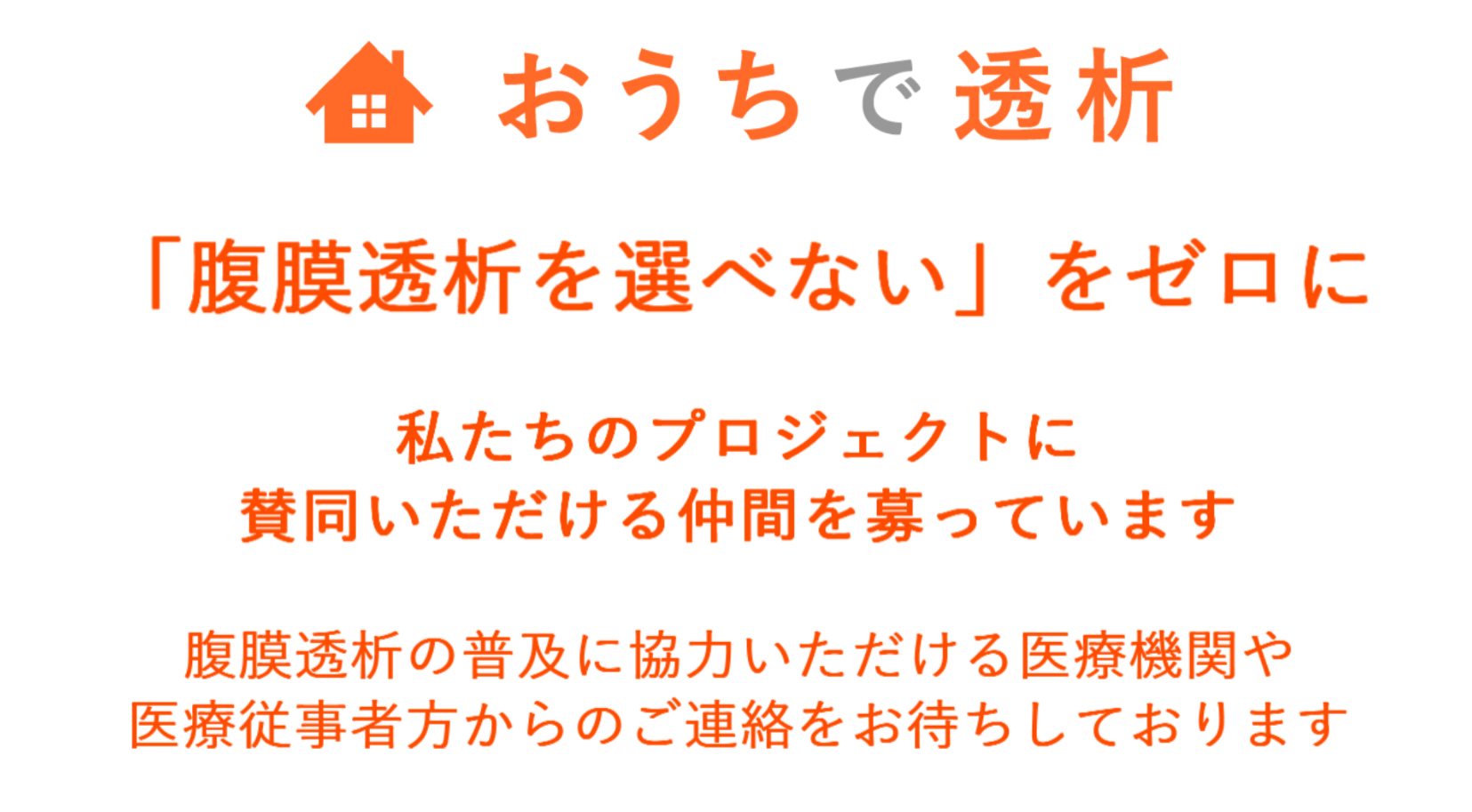松本先生インタビュー⑬腹膜透析と地域連携〜フランスでは56%がアシステッドPD〜


松本先生インタビュー⑬腹膜透析と地域連携〜フランスでは56%がアシステッドPD〜
文字サイズ
松本先生インタビュー⑬腹膜透析と地域連携〜フランスでは56%がアシステッドPD〜
[松本先生インタビュー⑬腹膜透析と地域連携〜フランスでは56%がアシステッドPD〜]
- 川原腎・泌尿器科クリニック(鹿児島県姶良市)
腎不全外科科長・腹膜透析センター長
松本 秀一朗 様
聞き手:
- 医療コンサルタント 大西 大輔(MICTコンサルティング株式会社 代表取締役)
- 医療法人明洋会 理事長 柴垣 圭吾 様
松本先生: このような考え方は、すでに2002年に慈恵医大グループのかしま病院・中野先生が論文で発表しています。腹膜透析を緩和ケアの一環として活用できるのではないかという提案でした。
また、2015年にはスペインから「パリアティブPD(緩和的腹膜透析)」という概念が提唱されました。これは、患者さんの苦痛症状を緩和し、最後まで見放されずにケアされていると実感できる治療法であると報告されています。私はこの定義はとても良いものだと考えています。
私は10年以上前、鹿児島に赴任し、腎移植と腹膜透析に携わっていました。意外だったのは、腹膜透析の患者さんが最も増えたことです。
その理由は、地域で提供されていなかったことに加え、私が強く勧めたわけでもないのに、話を聞いた多くの患者さんが「やりたい」と希望されたからです。これこそが日本の現実だと思います。
腹膜透析を希望される方は、高齢者を中心に多くの困難を抱えています。その解決策として、私は「できる方にはやってあげよう」と考え、積極的に導入を進めました。
しかし導入時の平均年齢は70歳を超えており、自分でできない方も多いため、支援体制が不可欠でした。そのため、2012年当時から、私は地域連携による支援の仕組みが必要だと考え、戦略的に取り組みを続け、現在では90例を超えるまでになっています。今も新たに導入中の患者さんがいますが、患者数は年々増えています。
2012年当時、私たちが参考にしたのはフランスの事例です。フランスにはHAD(Hospitalisation à Domicile:在宅入院制度)という制度があり、日本の慢性期在宅医療とは異なり、病院並みの医療を在宅で機動的に提供する仕組みがあります。
具体的には、手術翌日の早期退院、周産期の早期帰宅、がん終末期における在宅での抗がん剤治療、神経難病の気管切開・人工呼吸器患者の在宅ケア、そして在宅透析がその柱となっています。
医療依存度の高い方を在宅で支え、社会的入院を回避し、入院期間を短縮する制度であり、主役は看護師です。日本とは大きく異なります。
日本では訪問診療や訪問看護は、しばしば「肩叩きに行くだけ」と揶揄されますが、そのような業務は今後は医療というより介護や福祉に移っていくでしょう。
しかし、フランスのような形は日本でも実現可能だと考えています。実際、フランスでは腹膜透析患者のうち50〜60%がアシステッドPD(支援型PD)を利用しており、さらに8.6%は血液透析からの移行で緩和的腹膜透析です。
私はこの論文を知っていたため、日本でもこうした形を目指すべきだと考えました。そのためには訪問看護師のトレーニングが不可欠です。それまでの訪問看護は、慢性期患者に「元気ですか」と声をかける程度で、医療行為とは言い難いものでした。
だからこそ、看護師に腹膜透析という医療行為をしっかり教育し、実践できるようにする必要があります。
私が鹿児島で腹膜透析を始めたとき、いくつかのコンセプトを掲げました。 1つ目は、ソーシャルネットメディアを活用して連携システムを構築することです。
どうやって患者さんを集めるか、どうやって患者さんを上手に維持するか、どうやってアシステッドPDを支える連携システムをつくるのかを考えました。電話やFAXでは限界があるため、ソーシャルネットメディアを活用した連携が不可欠です。
2つ目は、医療・介護保険制度に医師自身が精通し、ソーシャルワーカー任せにしないことです。そして3つ目が、訪問看護師の育成です。
この3つが、私が2012年から取り組んできたアシステッドPDの基盤です。
その結果、10年後の今、地域では老人施設58箇所、訪問看護ステーション60箇所と連携できるようになりました。鹿児島県内には訪問看護ステーションが約90箇所あり、3分の2以上が腹膜透析患者の受け入れ実績を持つようになりました。
このような仕組みがあれば、病院外のアウトソーシングである訪問看護を活用し、入院しているかのように在宅でも腹膜透析を提供できます。特に自己管理が難しい患者でも、フルアシスト体制で在宅で腹膜透析が可能となります。